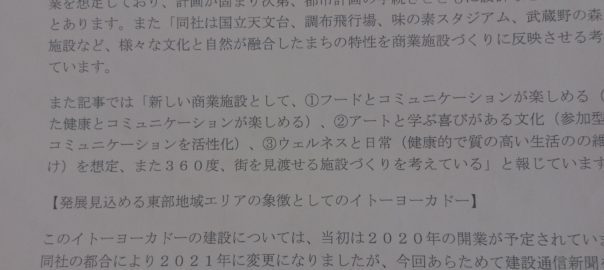府中市議会議員の 結城りょう です。
昨日(7月10日)付の読売新聞多摩版に、東村山市が市民サービス向上や業務の効率化につながる提案を、民間業者から公募するとの記事がありました。記事では「市が行う全ての事業や行政事務が対象」「提案は書類で受付、業者と関係部署との協議、市の幹部による審査を経て採否を決める」とあり、市外の業者からの公募も受けるとのことです。東村山市の渡部市長は記事のなかで「行政、市民、民間業者の三方にとってよい形となるような提案を受け入れたい」としています。
この記事にもありますが、民間のノウハウを活用する手法を「公民連携」(PPP)と呼び、府中市でも昨今、公共施設老朽化、人口減少に対応する手法として導入しています。後日ブログでも紹介しますが、先日、厚生委員会の視察で大阪府の大東市に赴き、介護の総合サービス化について話を聞いてきましたが、同市ではこの分野にも「公民連携」を取り入れるとのことでした。
確かに一面的に見ると、いわゆる役所の発想では「硬直的」ともいえる姿勢も目につきます。その点、民間企業は消費者の需要に対応するために、「機敏」に商品を開発し、消費者のニーズに応えなければ、生き残れません。同時に経営の効率化を図るという点では行政より優れているかもしれません。
ただこの点だけを一面的に評価すると、本来、住民に対する行政が果たすべき「公共サービス」の側面が希薄になり、目的が「利益優先」となること。そのために「効率優先」の側面が強調されるあまり「人件費の抑制」に走り、非正規職員が多数を占めるようになります。また業務や個別の方針課題を民間企業などに「丸投げ」することが習慣となり、スペシャリストとしての行政マンが育成されず、結果として住民サービスの質が低下するようなことになりかねません。あくまでも行政が主体となって、市民向けサービスを向上させることが大前提としての、民間手法の導入という発想が第一ではないでしょうか。
今後、府中市の行政における「公民連携」の問題について、私も調査したいと思います。