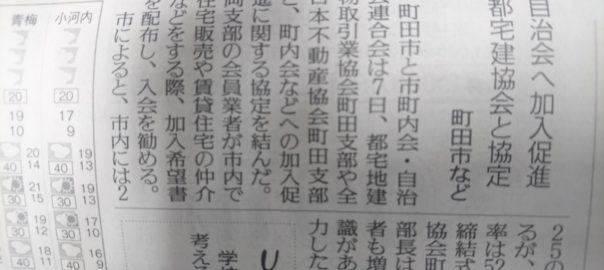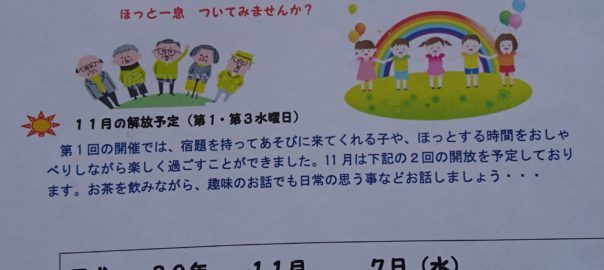京王線府中駅に「ぷらりと京王府中」が11月22日からオープンします

現在改装中の京王線府中駅直結の商業施設ですが、このたび11月22日からこれまでの「京王府中ショッピングセンター」から新たに「ぷらりと京王府中」に改称され新規オープンします。すでに10月26日から府中駅東側に食物販関係の4店舗がオープンしていますが、11月22日からは新たに7店舗がオープンします。jこれで府中駅改札東側においては食物販を中心としたエリアになります。
府中駅東側2階に新規オープンしたのは(10月26日)、業態では①ベーゲル、②すし、③おこわ・惣菜、④おむすび・惣菜の各店舗
また11月22日からは①スーパーマーケット、②ドラックストアー、③自然食品、④ベルギーワッフル専門店、⑤たい焼き、⑥洋生菓子、⑦洋服の直し、バック・靴の修理洗いなど。
お客様の問い合わせ先は、京王電鉄SC営業部中央地区SC事務所
電話042-426-8492(午前10時~17時まで)
結城亮(結城りょう)