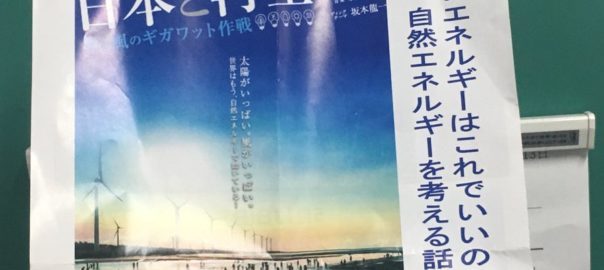調布飛行場 自家用機の運行再開問題・・「なぜ今」被災市民ら反発

今朝(9月11日)の東京新聞多摩版に、昨日開催された調布市議会の調布飛行場等対策特別委員会では、東京都が示した自家用機の自粛解除方針に対して、委員からは「拙速だ」との意見が相次ぎ、都の責任も追及する意見もあったと報じています。記事では同委員会に都の港湾局幹部も出席し、自粛解除方針を伝えたことに対して、委員の側は「なぜ事故原因の大きな一因となった遊覧飛行を都は見抜けなかったのか」「見過ごしてきた都側の注意義務違反の責任は」など意見に、都側も回答に窮したと報じています。
また記事では「『飛行場問題を考える市民の会』のメンバー、村田キヨさん(78)は『住民説明会の時には自家用機の飛行再開について何も言わなかったのに、その後すぐに3市に言ってくるなんて、だまし討ちだ』」などの声を紹介しています。
今日は府中市議会でも基地跡地等特別委員会が開催されますが、この問題で市の担当者からも説明があると思います。3市のひとつである府中市も先日、高野市長が都が発表した自粛解除方針には懸念を表明しており、市議会でも都の方針への批判の意見が出ることは間違いないと思います。都の安易な自家用機運航再開のための「自粛解除」方針に対して、住民生活の安全を守る立場から、都側の責任追及含めて、運行再開には慎重な極めて態度をしなければなりません。
結城亮(結城りょう)