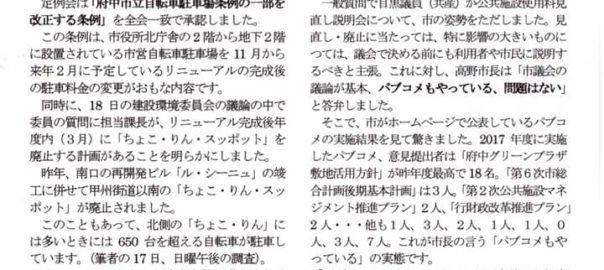障害者の介護保険優先原則「65歳問題」の解消を・・共産党議員団
6月の一般質問で、共産党議員団の服部ひとみ議員は、障害者の介護保険優先原則、「65歳問題」の解消について質疑をしました。
障害のある方が65歳に達すると、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行させられます。そのため、障害者福祉制度では非課税世帯には原則無料ですが、移行によって利用料負担の発生や、サービスの量が減ることになります。65歳になると「要介護4では障害者のサービスが認められず、5で認められる」あるいは、「受けていたサービスが半分に減る」などの声が市民からよせられています。
そこで介護に移行しても同一事業者からサービスを受けることが可能となる共生サービスの新設を機会に、「65歳問題」への対応と市の考えを質しました。市内の65歳以上の障害者のうち介護保険サービスのみのり利用者は1639人(34.2%)、障害福祉サービスの上乗せ支給は30人(0.6%)、ALSや視聴覚障害と要介護5が該当。「原則として介護保険サービス移行後は、全員が負担増」との答弁でした。この答弁に対して服部議員は、要介護度が4に下がり月100時間受けていたサービスがガイドヘルパー1日30分を残してカットされ、不足分が自己負担になった例を示して、こういう事態にならないように質しました。
市の答弁では「一律、機械的に削減をすることはない」「必要と認められる場合には、障害サービスの支給を決定する」ということでした。服部議員は質疑の最後に「障害者が高齢になっても必要なサービスを受け続けることができるように、介護保険優先原則の撤廃を国に求めるように要望しました。
結城亮(結城りょう)