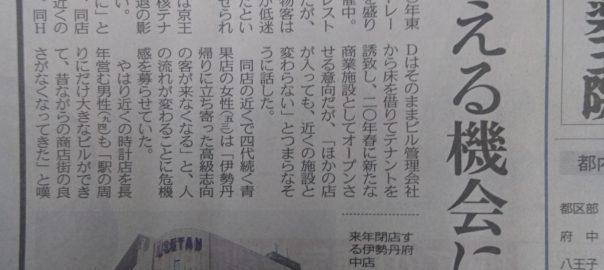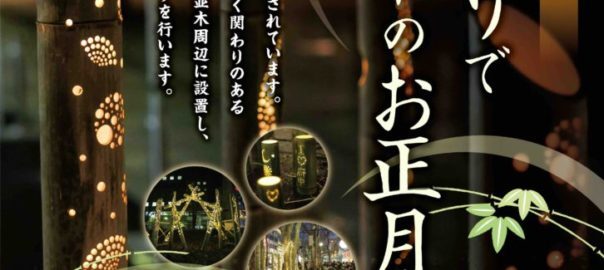府中・武蔵国府跡国司館復元 オープン以来人気呼ぶ

今朝(1月16日)の毎日新聞多摩版に、本町にある国指定史跡「武蔵国府跡」に、奈良時代の国司館(こくしのやかた)を復元した広場がオープンして人気を呼んでいると伝えています。記事にもありますが、「貸出ゴーグル型スコープを使うと当時の風景を再現したVR映像を楽しめます。
「武蔵国府は約1300年前の飛鳥~奈良時代初めから平安時代の終りにかけておかれた行政府、武蔵の国の政治、文化の中心として栄えた。国司館は武蔵国を治めるために中央から派遣された官吏が仕事をしたり生活をした建物」とのこと。この広場はJR府中本町駅近く、昨年11月にオープン。府中市が国と都の補助金をうけて、約7800平方メートルの面積を整備したものです。記事では「VR映像で国司や家康を演じているのは、市内にある都立農業高校の生徒12人。再現した当時の衣装を着て撮影して、CG映像に加工した」とのことです。記事は「ふるさと文化財課の江口課長のコメントとして、『未来にある生徒たちに史跡を伝えていってもらいたいと考え、出演を依頼した』」。
ちなみに開演時間は午前9時~午後5時、スコープは午後3時まで、広場の管理事務所は無料で貸し出しているとのことです。
ぜひみなさん、一度ご来場ください。
結城亮(結城りょう)