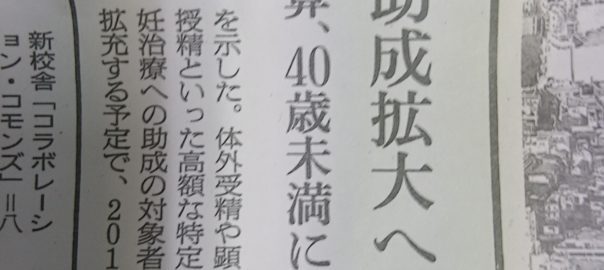府中市でも小中学校の特別支援教育、教員の配置改善を!・・共産党都議団が都議会で質問
27日の東京都議会で共産党都議団の原田あきら都議が一般質問で、小中学校の特別支援教育に対して、教員の配置基準改善などの支援を抜本的に求めるよう小池知事に求めました。
原田都議は、都が情緒障害通級学級で、ADHD(注意欠陥、多動性障害)など集団生活に困難を抱える子供に特別の指導を行い、困難を克服するなど、教員の専門性を磨き教育内容を充実してきたと紹介しました。「情緒障害学級で培われた教育技術を継承発展させることが重要だ」と強調。
都は2016年度に小学校の通級学級を、拠点校の教員が各校を巡回指導する特別支援教室に変更しました。これにより、支援をうける子どもが増えた一方で、教員の配置基準が切り下げられ、杉並区では18年度当初の児童数342人に対して、通級学級基準では教員数46人になるところを、36人しか配置されていないのが現状とのこと。
原田都議は保護者や教員から「子供に必要な授業時間数や教育内容が確保できない」との声がでていることを紹介。来年度から特別支援教室を本格事実施する中学校も含めて教員配置基準を改善するよう求めました。
中井敬三教育長は、原田氏が指摘した声が出ている事実を認め、教員配置基準について「各学校現場の実態把握結果をふまえ、適切な巡回指導体制を検討する」としています。
共産党都議団のこうした要望をふまえ、都も前向きな施策実現を求めると同時に、私も府中市に対して学校現場の教員の声を伺い、府中の特別支援教室に対する教員配置の拡充を求めていきたいと思います。
結城亮(結城りょう)