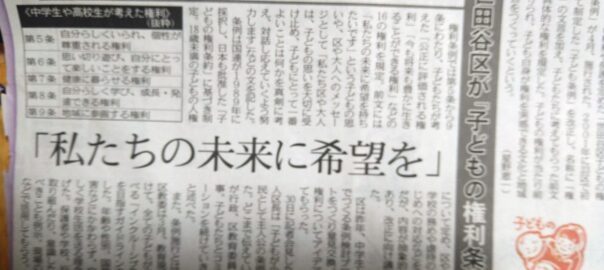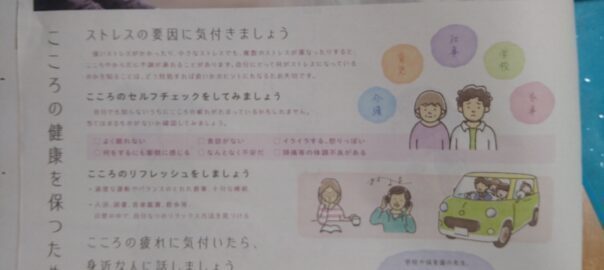府中市 女性活躍・・東京都が女性活躍条例制定にむけ都議会に条例案を提出へ(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
★雇用、就業、性別による思い込み解消をめざす
先日のTBSネットニュースによると、東京都は雇用・就業分野での「女性の活躍を推進する条例案」を発表したと伝えています。制定されれば、全国の都道府県では初めての条例になるということです。 同ニュースによると「都が発表した『女性の活躍を推進する条例』は、雇用や就業といった『働く場』において、『性別による無意識の思い込み』を解消し、女性の活躍できる環境を整えることを目指すもの」としています。また同 条例案では、「都内の企業に対して、①特定の性別に偏らない組織作り、②賃金や役職などの男女間の格差解消、③生理休暇取得など女性特有の健康課題への配慮などの取り組みを主体的に行うよう求める」とのことです。
★都民に性別に関する偏見に関心をもち、理解を深めることを求める
また、都民一人ひとりに対しても、「性別に関する偏見に関心をもち、理解を深めるよう求める内容」などが盛り込まれ、「都はそうした環境整備に必要な情報提供や啓発を行う」とのことです。 東京都では、12月から行われる定例の議会に条例案を提出する予定であり、制定されれば、雇用や就業分野での女性の活躍に関する条例は全国の都道府県で初めてになるそうで、ただし罰則規定は設けないとのことです。(参考 11月25日付、TBSネットニュースから)
★府中市の現状は審議会メンバーの女性登用率は34%程度(2023年当時)
府中市においても、女性活躍という点においては、市の審議会において女性登用を促進するために、市にデーターバンクを創設しています。府中市では市の付属機関である審議会などに女性が参画できる環境を整備するために、「府中市女性人材データーバンク」を創設、30人程度のメンバーを募集しました(2023年)。
記事では現在(2023年当時)、市にある56の審議会には委員数計832人のうち、女性は281人、登用率は約34%とのことです。記事にありますが府中市は女性委員の登用を40%以上を掲げているが、伸び悩んでいます。市としては当面40%以上の登用をめざしています。データーバンクメンバーの対象は①18歳以上、市民以外でも可、②地域活動や職歴、参画を希望する分野などを記入して応募することです。※問い合わせは「フチュール」電話042-351-4600へ
私も以前、議会で市の防災委員のメンバーに女性の多数登用を提案したことがありますが、こうした試みは評価できるのではないでしょうか。自治体の審議会委員というのは「敷居が高い」存在であり、一般的には馴染みがありません。しかし行政の側がこうした「壁」を低くして、募集をすることで少しでも女性の審議会メンバーが増えることは、積極的な姿勢で評価できます。
~今回の東京都による女性活躍条例が制定されれば、罰則規定はないものの都内の自治体に対して大きな影響力を与えるものと思います。ぜひ府中市においても、官民連携した女性登用の場が増えることを期待します。(府中市議 ゆうきりょう)
※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp 電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202
※ ゆうきりょう の朝の駅頭市政報告は、原則、毎朝下記の予定で行っています。駅頭では「市政通信」を配布しています。市政相談、生活相談なども受け付けています。なお雨天時や、自身の都合により中止の場合もあります。お気軽にお声をおかけください。
月曜日・・西武線多磨駅東口
火曜日・・京王線多磨霊園駅南口
水曜日・・京王線東府中駅北口
木曜日・・西武線多磨駅西口
金曜日・・京王線多磨霊園駅北口、※原則、朝8時まで