府中市 こころの疲れ こころの相談窓口(広報ふちゅう令和7年3月1日号) (府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)
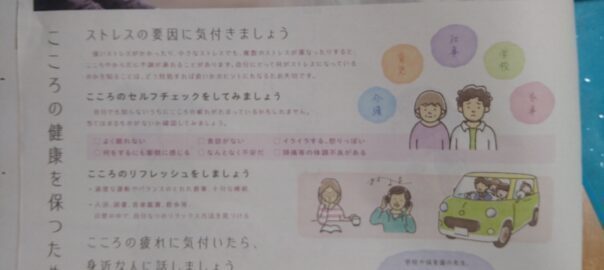
府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
「広報ふちゅう」3月1日号で府中市が開設している「こころの相談窓口」についての記事が掲載されています。毎年3月は「自殺対策強化月間」で東京都はじめ、市区町村でも、こころの相談窓口広報キャンペーンなどしています。
(1)「こころとからだの健康」に関する保健相談室(保健センター、電話042-368-6511)
(2)「子ども(自分)自身、子育てや家庭の悩みや不安」に関することの相談窓口(①子育て世代包括支援センター「みらい」電話042-319-0072)、②子ども家庭支援センター「たっち」電話042-354-8701)
(3)「高齢の方自身、身近な高齢の方の悩みや不安」に関する相談窓口(①高齢者支援課 電話042-335-4496)、②各地域包括支援センター)
★多摩市がNPO法人との間で、自殺や孤立相談などの連携協定を締結
以前ですが読売新聞多摩版に多摩市が、NPO法人「あなたのいばしょ」との間で、自殺や孤立などの相談をめぐる、連携事業協定を締結したとの記事があります。記事では「同NPOは、自殺願望がある人などからチャットでの相談を24時間受け付けており、市と連携して相談者への具体的支援につなげることを目指す」とあります。
記事によると、同NPOのチャット相談は、誰でも無料で匿名で利用できるそうで、「協定では、相談者が多摩市民と判明した際には、相談者の了解をえて市側と情報を共有し、相談者がかかえる課題の解決を図るとしている」。同NPOと連携協定を結んだ自治体は、品川区と奈良県生駒市など6例目で、多摩地域では初とのことです。記事のなかで多摩市の阿部市長は「今の子どもたちに寄り添うには、SNSでいつでも対応できることが大切だ」とし、同NPOの大空理事長は「相談窓口だけでは問題解決が難しく、地域での継続的な支援が必要だ」としています。多摩地域では日野市もNPO法人が連携して相談体制をとっています。
★府中市にも自殺防止対策計画などはあるが
私も以前、府中市議会の一般質問で市の自殺対策、孤立対策の相談窓口などの取り組み強化を求めて質疑をしましたが、当時はコロナ禍以前ではありましたが、市の自殺対策、相談窓口の体制などについて新たな取り組みの強化が求められていました。すでに府中市も自殺総合対策計画を立案していますが、当時の質疑で私は①自殺防止は庁内各課の連携が大事であり、生活困窮の状況を認識できる部署である生活援護課、納税課をはじめとする、幅広いセクションと連携してほしいこと、
②同時に行政だけでは対応しきれない課題もあり、ぜひNPO団体、民間、市民団体などとも連携してほしい、
③15歳~30歳代にかけて死因の一番の理由が「自殺」であり、若者対策をぜひ強化してほしい。
④神奈川県座間市で起きた事件(自殺を願望する9人の若者がSNSを悪用されて、殺害された事件)にあったが、SNS対策をぜひ強化してほしい、
⑤自殺予防策として、ゲードキーパーの養成を強化してほしい、
⑥自殺未遂者、自死遺族への支援を具体化し、強化してほしいことなどを要望しました。
行政による自殺防止対策は、どの自治体もあまり成果をあげていないような様子が伺えます。その意味で今回の多摩市(日野市でも実施)による民間団体との連携協定は、大変意義あるものであり、ぜひ官民連携による自殺防止、孤立防止の相談窓口対策を府中市においても、検討できないものか、今後も要望したいと考えるものです。※ 府中市自殺防止対策概要
※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp 電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202



