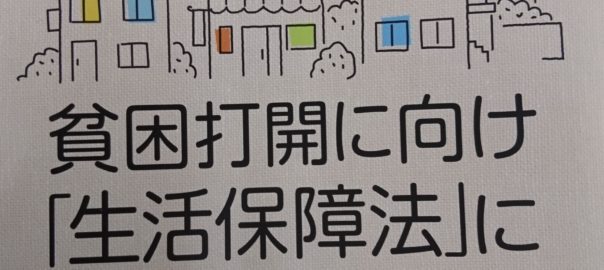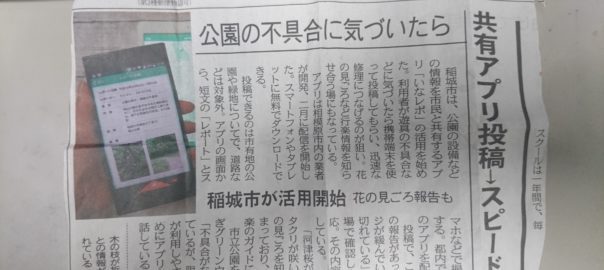狛江市長がセクハラ報告・・副市長、本人同席の臨時庁議で

【読売新聞、朝日新聞多摩版の報道から・・副市長が事実上の「辞職」勧告?】
今朝(19日)の読売新聞と朝日新聞多摩版に、狛江市の高橋市長によるセクハラ疑惑について、市庁内の動きを報じています。読売の記事では、18日の臨時庁議において副市長が「(市長による)セクハラ行為は確認できた」と報告。「市長という立場を利用して卑劣な行為を行ったにもかかわらず、『身に覚えがない』と言い逃れ、職員、市政に及ぼした影響は計り知れない」と糾弾。さらに「身の処しかたを判断してほしい」と報じています。
これが事実なら市の幹部が高橋市長に「辞職」を突き付けたに等しいのではないでしょうか。職員組合からも、また副市長からも完全に「NO」と言われたのですから、市長もこれで「アウト」に近い状態ではないでしょうか。
【狛江市庁内の自浄能力に健全性を感じる】
高橋市長をここまで追い詰めた共産党狛江市議団はじめ、共闘した他会派の議員の方々、そして連帯した市民のみなさん、また今日の記事を見る限り、狛江市には市長がこうした問題を起こした際に、庁内で「自浄能力」を発揮していることに、狛江市の健全性も感じました。
まさにこの自浄能力という点で言えば、狛江市のほうが今の安倍内閣と霞が関と比較して、よほど健全性を発揮しているのではないでしょうか。
結城亮(結城りょう)