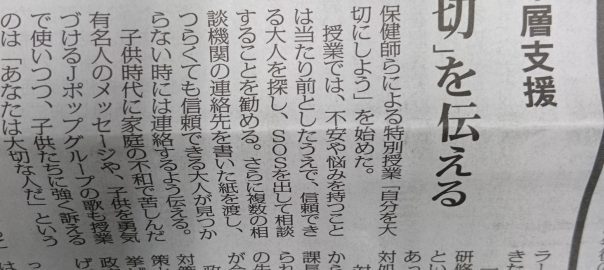平成の軌跡 貧困と社会の分断(毎日新聞)を見て当時を振り返る

【格差と貧困を可視化した日比谷公園の年越し派遣村】
昨日(1月31日)の毎日新聞オピニオン欄に、2008年の年末の日比谷公園にできた「年越し派遣村」を振り返りながら、今日の生活困窮者の状況について問う特集記事があります。紙面では当時、「派遣村」の「村長」を務めた湯浅誠氏が振り返るかたちで報じられています。湯浅氏は当時を振り返り、当時リーマンショックで製造業の職場を派遣切りされた非正規雇用労働者が日比谷公園に集まり、テレビで報じられたことが、日本の貧困社会の可視化をもたらしたと語っています。湯浅氏は「派遣村に対する日本社会の関心の高さは、これまで実感のなかった貧困が急に目の前に現れた・・そのインパクトだったと思います」と語っています。また当時、政府が国民の貧困層の割合を示す「相対的貧困率」(06年時点で15.7%)を09年10月に初めて公表したことをあげ、「社会の雰囲気を大きく変えた」と言います。そして今日の状況を振り返り、現代の若者が高齢者を切り捨てるような意識をもっていることを憂い、お互いが「目線をあわせる」ことを意識して活動することの重要性を指摘しています。
【あれから10年、日本の貧困はさらに深刻になってしまった】
私は当時(08年12月)、建設労働組合の事務局に勤務しており、この「年越し派遣村」に支援物資を届けに行ったことを覚えています。31日の午前中でしたが、すでに派遣切りされた方々が集まり始めており、湯浅さんを中心にたくさんのボランティアの方々が集まり、受け入れ体制の準備をしていたのを、よく覚えています。その後昼過ぎのニュース報道で、日比谷公園の「派遣村」にぞくぞくと人が集まってきて、厚生労働省の講堂が開放され、派遣切りされた方々が、急きょ収容されたニュースを覚えています。あの時以来、一時的に日本の社会と政治の流れが「変わった」ことを実感しました。
あれからちょうど10年が経つわけですが、日本の格差と貧困はよりいっそう広がってしまったと思います。09年には民主党政権が誕生し、多くの国民が期待しましたが、結果は裏切らました。その後、第二安倍政権では格差と貧困、そして戦争する国づくりと憲法改悪が現実の政治日程にのぼるほどになってしまいました。
【国民、労働者がなぜこれほど弱くなったのか・・労働組合の反撃が弱いこと、社会党の右転落と解党が決定的】
私はなぜこれほどまでに、国民、労働者が貧しくなったその原因を問われれば、ひとつは国民の反撃、とくに労働組合のたたかいが抑えられていること。また日本の政党戦線の状況においては、かっての社会党が「右転落」し、共産党との革新共闘を分断したことと、その社会党が解党されたことが大きな原因にあると思っています。今の日本社会は「階層」から「階級」ともいえる格差社会となり、貧困な状況においこまれると生涯、貧困から脱することができない状況になっていると思います。私も議員になり、住民生活の実態を見ると、このことを肌で実感します。しかしこれからも、絶対にあきらめることなく、運動と議会の論戦で格差と貧困社会をなくすために、頑張る決意をあらたにしています。