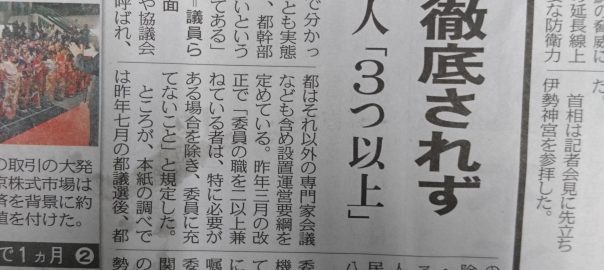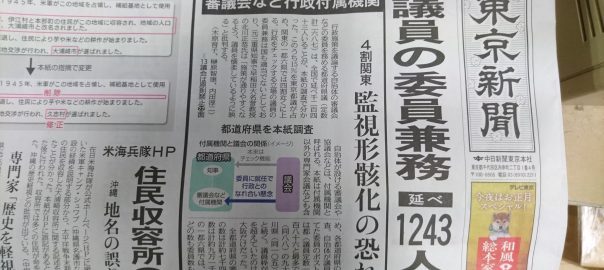「保育施設立ち入り65%、自治体・点検不十分」(読売新聞)
【読売調査では、自治体指導内容は東京都が最も低く15%】
今朝(8日)の読売新聞1面トップと3面で、自治体による保育施設への現地調査が対象施設の65%にとどまっている実態が掲載されています。私は昨年1月15日付のブログで、当時の毎日新聞2面において、「厚労省方針 重大事故防止策」「保育施設を巡回指導」と、この問題を報じていることを記載しました。今回は読売新聞が独自調査でこの問題を報じてます。記事では47都道府県、20政令市、48中核市で実施、「その結果、各自治体が対象とする計約3万4000ヶ所の施設のうち、立ち入りを受けていたのは約2万2000ヶ所、3分の1が未実施だった」とあり、「とくに東京都が最も低く15%」とあります。記事では「自治体の指導内容は、避難訓練の実施(防災)が最多、健康診断を適切に実施していない、職員配置」が最も多いとあります。
【書類で済ますケースも多々ある】
この読売記事にもりますが、「自治体の立ち入り(調査)は、児童福祉法などで原則、年1回以上行うことが求められている。施設の人員配置や防災対策などが基準を満たしているかを調べ、問題があれば改善を促す」ことが目的です。この読売の記事ではなぜ現地調査が実施されていないかについて、「保育施設が急増するなか、人手不足などで実施しきれていない」とあり、書類検査で済ませているケースもあるとあります。ちなみに昨年の毎日新聞の記事では「自治体に新たに『巡回指導員』を配置し、認可外も含めて月1回以上巡回する」「助言に法的強制力はないが、改善しない施設については、自治体が改善指導にのりだす」とあります。
【府中においても現地調査の徹底を求める】
私もこの記事が掲載された際、市の担当者にこの記事を見せ話を伺いましたが、府中では実施しているとしていましたが、今回の読売記事をうけて再度、担当者に伺いたいと思います。保育士さんが不足するなか、安全安心の保育サービスがないがしろにされている保育所は多数存在することが予想されます。議会においても待機児童解消を優先する質疑は多いのですが、この種の調査対策については質疑が少ないように思います。実際、私も市内の認可保育所において臨時保育士さんの不適切な指導が発生していることを相談に受けてこともあります。安心安全の保育のためにも、再度この問題についても取り上げたいと思います。