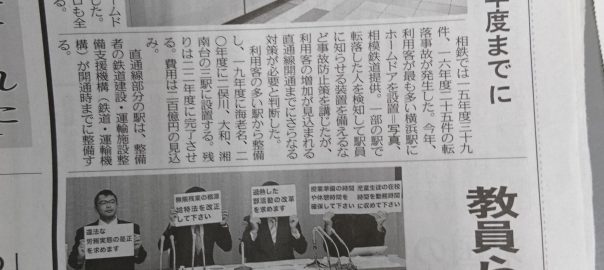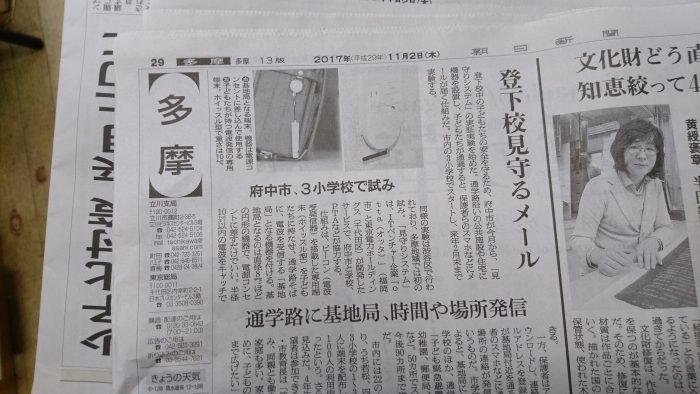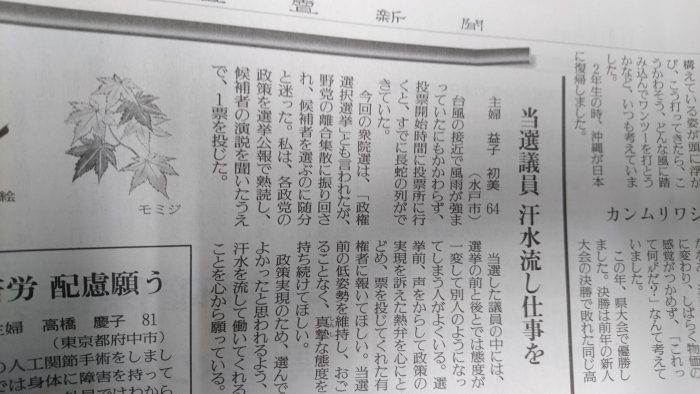「保育事故」に読者から反響 安全確保した施設作りを(読売新聞)
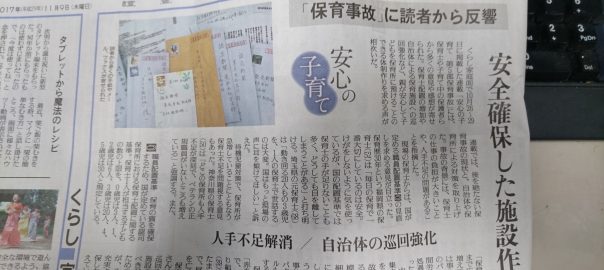
★国の保育士配置基準では安心安全の保育を守れない
今朝(9日)は京王線東府中駅北口であいさつ、午前中は一般質問の相談、午後はニュース配布、辻立ちなど。さて今朝の読売新聞くらし面に、同紙が連載した「安心の子育て 保育事故」のシリーズ記事に対し、多くの読者から反響が寄せられたことが掲載されています。記事では「現場の保育士からは、国が定める職員配置基準の見直しを求める意見が目立った」とあり、「埼玉県の元保育士(68歳)は『動き回る20人もの3歳児を、1人の保育士で世話するのは大変。国はもっと現場の声に耳を傾けてほしい』」「神奈川県の保育士(50歳)は『どこの保育所も人手不足が深刻で、ベテランの正規職員がいないところも増えている』」。
保育事故が全国でも相次いでいますが、これは至急対策を打たなければならない課題です。記事では「保育事故を防ぐため、認可外保育所で昼寝中の長女を亡くされた阿部一美さんは『自治体は保育施設の巡回を強化するなどして、各施設の状況をきちんと把握するべきだ。待機児童を解消するための保育所の増設は重要だが、同時に保育内容を充実させ、子どもの安全を確保しなければならない』と訴えている」。
★保育士確保は政治の責任で
私も2015年12月議会で、市立保育所の保育士の配置基準を見直すよう求めたことがありますが、私立保育所ではさらに大変な状況だと思います。以前、保育士を希望する方が、認可外保育所における保育士さんの幼児を扱う光景を見て、驚愕したと語っていました。私もそれを聞いて驚きましたが、保育士さんの待遇改善をあわせて対策を打たなければならないと思います。子育てできる社会環境を早急に整備することは、政治の責任です。私もまた議会で取り上げたいと思います。