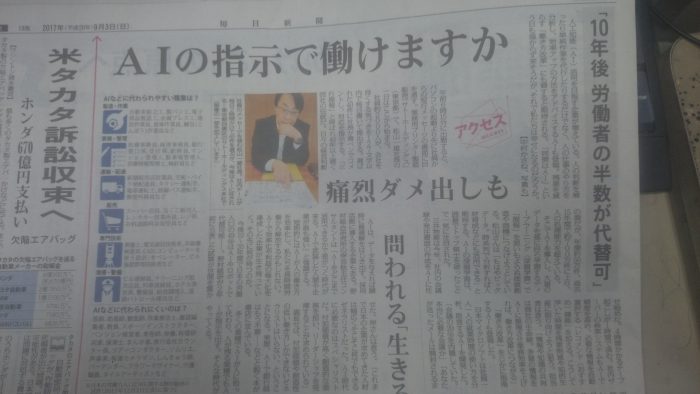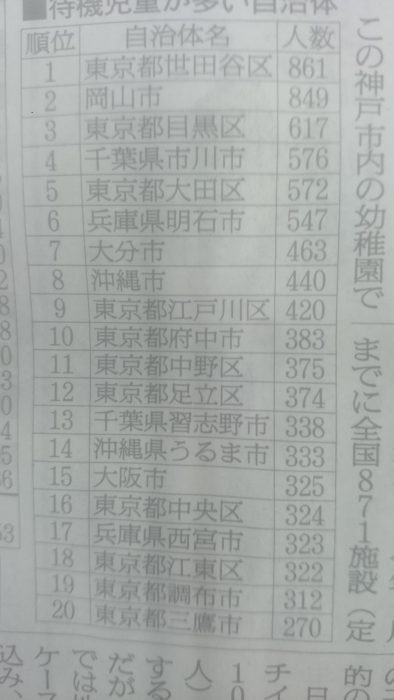「米 トイザらス破産手続き申請も選択肢に」・・NHKニュース
今日(7日)の午前中のNHKニュースによると、「アメリカの大手おもちゃ販売チェーン、トイザらスがネット通販に顧客を奪われて経営不振に陥り、破産手続きの申請を選択肢の一つとして検討している」と報じています。
NHKニュースによると「アメリカの複数のメディアは6日、トイザらスが負債を整理するために大手法律事務所と契約を結び、経営再建に向けた選択肢の一つとして破産手続きの申請を検討していると伝えました。トイザらスは、アメリカ国内だけでも800店舗以上を展開する大手おもちゃ販売チェーンで、巨大な店内に大量のおもちゃをそろえ、例年クリスマス商戦の時期は多くの家族連れで賑わっています。しかし、ここ数年はアマゾン・ドット・コムをはじめとするネット通販に顧客を奪われて売り上げの減少に歯止めがかからず、おととしの年末にはニューヨークのタイムズスクエアにあった旗艦店の閉店を迫られました。トイザらスはNHKの取材に対し、『来年返済期限を迎える負債に対処するため、さまざまな選択肢を検討している』」と伝えています。
トイザらスについては、京王線府中駅そばにある、「くるる」(商業ビル)のなかにも店舗を構えているので、大変気がかりなにニュースです。府中駅南口の再開発ビル「ル・シーニュ」がスタートしてから、「くるる」の人の流れも少なくなっているように私は思いましたが、その矢先のニュースです。府中の場合、昨年には伊勢丹の縮小報道もありましたので、府中駅の中心市街地活性化という点からも、今後のトイザらスの動向が気になります。