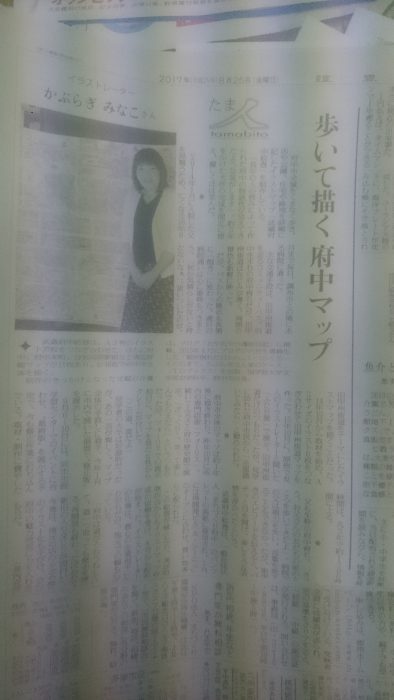学校教員の長時間労働解消のために、勤務時間管理と専門スタッフ増員など予算要求・・中央教育審議会特別部会
今朝(30日)は京王線東府中駅であいさつ、赤旗拡大、一般質問準備など。さて今朝の読売新聞には、教員の長時間労働の解消に向けた対策を検討している中央教育審議会の特別部会の記事が報道されています。記事では「(中央教育審議会・特別部会)は29日、タイムカードを使った勤務時間の管理や、事務作業を代行する専門スタッフの配置などを盛り込んだ緊急提言をまとめた。文部科学省は提言を受け、来年度予算の概算要求にあわせて具体的な対応の検討を進める」とあります。
さらに同提言では「まず教員の業務を見直す基本として、校長や教育委員会に対し、すべての教職員の勤務時間を客観的に把握するよう求めた。その方策として、タイムカードや、ICT(情報通信技術)を活用して退勤時間を記録できるシステムの導入などを促した。文科省の2016年度調査では、タイムカードなどを使い、勤務時間を管理している小中学校は3割弱にとどまっている」と報道されています。
私も6月議会で、教員の長時間労働の改善を求めて一般質問を行いました。実際に学校現場の教員の方に聞くと、研究会の準備や報告書の作成をはじめ、児童や生徒たちと向き合う時間がなく、朝8時前に出勤して夜は20時~21時ぐらいまで拘束される実態もあり、仕事が終わらないために休日出勤も当然の状態、本当に悲痛な声を伺いました。教員の長時間労働の問題の解決は簡単ではないでしょうが、少しでも前進することを願い、引き続きこの問題、私も注視していきたいと思います。