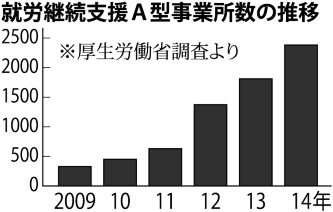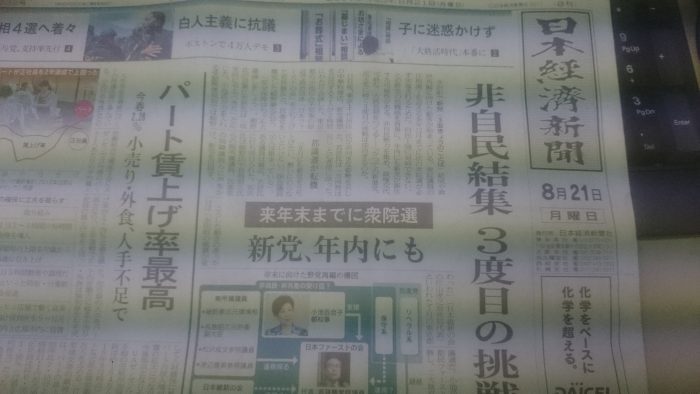「教員定数3800人増、要求 負担減、小学英語も視野(文科省)」(東京新聞)
今朝(25日)はJR北府中駅であいさつ、午前中、市議会建設環境委員協議会、午後一般質問準備、夕方に宣伝を予定。さて今朝の東京新聞2面に、文部科学相が来年度の概算要求において、公立小中学校の教員の定数増を要望している記事があります。それによれば定数増は3800人、記事では「長時間労働が深刻な教員の働き方改革を進めると同時に、次期学習指導要領に沿った授業を円滑に実施できるよう、小学校で英語などを専門に教える『専科教員』の増員を目指すのが柱」としています。2020年度から各小学校では英語が教科となり、授業のコマ数も増えます。府中市でいえば、来年度から小学校では「土曜授業」もスタートするなど、授業数増加と教員のさらなる多忙化が予想されます。なお記事では「校長や副校長、教頭が受け持つ業務を軽減し、学校の運営体制を強化するため、事務職員400人や主幹教諭100人の増員も求めた」とあります。
学校の教員はますます忙しくなっています。私も6月議会でこの問題を取り上げましたが、国と教育委員会と学校現場が一体で、戦略的に子どもたちのより良い教育と、教員の負担軽減と子どもたちに向き合える学校現場にするために、私も関心をもってこの問題、臨みたいと思います。