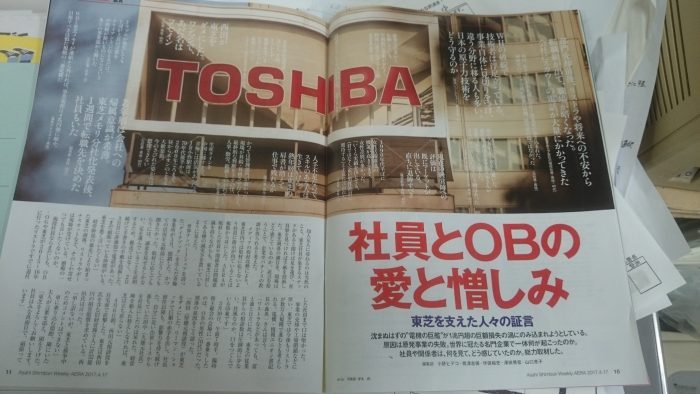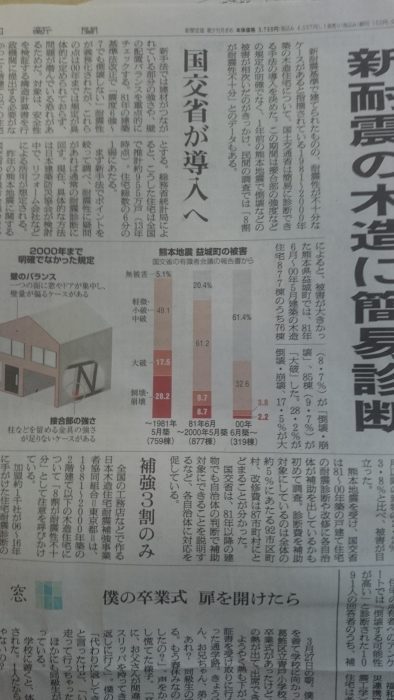「埼玉県内で人並みの生活、月収50万円必要・・埼玉県労連が調査」(朝日新聞デジタルニュース)
今朝(17日)は西武線多磨駅であいさつ、午前~午後にかけニュース発行準備など。さて今日の朝日新聞デジタルニュースで埼玉県労連(埼玉県労働組合総連合)による、県民生活調査の記事が配信されています。このニュースでは、「埼玉県内で人並みに暮らすには月約50万円の収入が必要で、子供が大学に入ると支出が急に増え、奨学金がないと成り立たないとする調査結果を、埼玉県労連と有識者がまとめた。『賃金の底上げとともに、教育や住宅の負担を下げる政策が必要』と指摘している。調査は、昼食を食べる場所や日ごろの買い物の場所や支出など、日常生活でのお金の使い方を聞く『生活実態調査』と、生活に必要な持ち物を聞く『持ち物財調査』のアンケートを、昨年1月に埼労連の組合員など3千人に依頼し、3カ月で597人(有効回答率約20%)が答えた。その分析で、回答者の7割以上が持つ物を『必需品』とし、それを持つ生活を『普通の生活』と定義。回答者がよく買い物をしている店などで実際の価格も調べた。こうした積算で、次の各モデルの結果が出た。いずれも夫は正社員で妻はパート勤務、車はない設定」。
①【30代夫婦で小学生と幼稚園児】さいたま市郊外で月5万5千円の賃貸住宅(2LDK、約43平米)で暮らす1カ月の生活費は▽食費約10万8千円▽交通・通信費約3万8千円▽教育費約2万7千円などの計約43万円となった。たとえば洗濯機は約6万円のものを国税庁の決まりをもとに耐用年数を6年として割り算し、月額を836円とするなどして、家具・家事用品の月額負担は1万8356円と積算した。08年の前回調査と比べ、教育費と教養娯楽費が合計で3万円近く増えたほか、交通・通信費も1万円余り増えるなど、約6万8千円増えた。この支出のためには、税や社会保険料を加えた額面で、約50万円の月収(年収約599万円)が必要だ。しかし、厚生労働省の調査によると埼玉県内の30代男性の平均年収は約411万円と、200万円近い開きがある。 ②【40代で中学生と小学生】30代より食費と教育費がそれぞれ約1万円増える一方、教養娯楽費は約1万3千円減るなどした結果、額面の月収は約54万円(年収約647万円)が必要。平均の485万円との差は少し縮まる。 ③【50代で大学生と高校生】東京の私大に通わせる前提で▽教育費が40代よりも約9万円多い約13万円▽交通・通信費も同1万1千円多い約5万円と大きく増える。教養娯楽費を30代より1万7千円余り少ない約2万8千円に抑えるが、全体の支出は約58万円で、税などを加えた額面は約68万円(年収約821万円)と、平均の545万円を276万円上回る。調査をまとめた静岡県立大学短期大学部の中沢秀一准教授は『妻のパートでは足りず、子供は奨学金を借りる。無償の奨学金や住宅補助の制度を充実させないと子供の将来はさらに厳しい』と指摘している」とあります。
読むとわかるように、お子さんを大学に進学させるには教育ローンが必須、お父さんのお小遣いなどわずかな金額、老後のための蓄えもできず、さらに超過密労働社会、インフレと増税、年金削減など、国民がまともに生活ができる環境が、日本社会にはないということわけです。