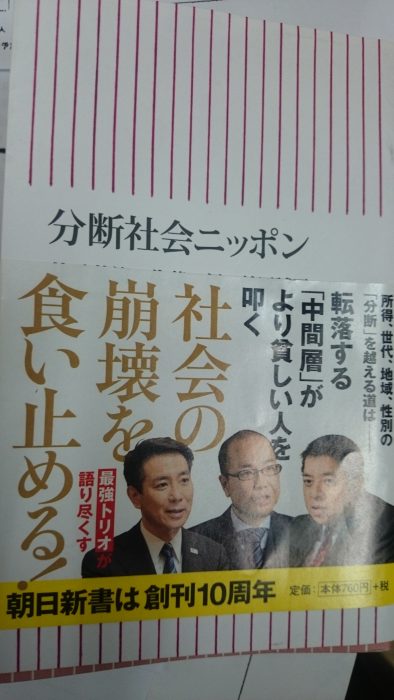東芝蝕む「原発」赤字、損失最大7000億円、焦げ付きは国民にツケ(東京新聞)
今朝はJR北府中駅前であいさつ、午前、午後は打ちあわせ、午後に宣伝を予定。さて今朝の東京新聞26~27面「こちら特捜部」において、東芝に関する記事があります。記事では、東芝が米国の原発事業で最大、7000億円の赤字をだしたことで、政府系金融機関、日本政策投資銀行に支援を求めていることが報じられています。紙面では「リスクを抱えた輸出戦略は見直すべき」との見出しをかかげ、「福島の事故を機に世界の原発事業の流れは変わったのに、東芝は積極姿勢を取り続けた。環境の変化に目をつぶり、経営陣が『チャレンジ』とハッパばかりかけるような会社だ。経営の甘さのツケがまわったのでは」と論じています。
東芝といえばこの府中市にも長い歴史をもつ事業所があり、市議会にも組織内議員もおくりだし、ラグビーなどスポーツクラブも旺盛に取り組むなど、府中の有力事業所でもあります。しかしながら、今日の東芝は不正会計問題もあり、今後、府中事業所もどうなるか(リストラなど)不安は隠せません。この記事の最後には、デスクメモとして「福島の事故後、市民の反対で、国内では原発の新設をできない状況なのに、日本の企業が海外で原発をつくること自体、おかしい。それでも企業が海外で受注をめざすというなら、その動きは止められないが、資金は民間の銀行から借りればいい。国民の税金に頼るのはおかしい、と言いたい」と結んでいます。私も全く同じ認識です。みなさんはどうでしょうか。