国民健康保険料、市区町村43%で増、都道府県移管、国費で伸び抑制
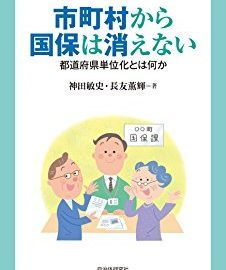
【毎日新聞の報道から】
昨日(31日)の毎日新聞朝刊1面で、4月より市区町村から都道府県に運営主体が移管される国民健康保険の保険料が、43%の自治体で増(656市区町村)、57%(828市区町村)が下がり、据え置きは2.6%(30市区町村)との記事が掲載されています。また保険料が上昇する自治体のうち、90%超は上昇幅が3%以内とのことです。また記事では「制度変更にともない保険料が急激に上がりかねないと懸念していた自治体も多かったが、移管支援を目的に国が約3400億円の公費を投入するため、保険料の伸びは一定抑制される」とあります。「実際の保険料額は、今回の保険料水準をもとに、市区町村が6月までに決める。保険料の上昇を抑えるため、独自に市区町村が一般会計から繰り入れた場合、据え置きや保険料が減少となる可能性もある」とも報じています。
【結城りょうの視点・・国民皆保険制度を守るために国費増額、市区町村からの繰り入れを求める】
私は昨年11月26日付ブログ「来春実施の国保の都道府県化で保険料は1人あたり1.3倍に(都が試算)」、10月19日付ブログ「国保赤字 税金穴埋め容認・・厚労省 保険料上昇で反発懸念」、12月22日付ブログ「府中市が来年度国民健康保険料の値上げ見おくる」でも、この問題を記載しました。
共産党府中市議団は2月の市議会一般質問で赤野議員が、この問題を質しました。市は18年度予算で法定外繰入金は27億円とあり、仮に6年間でこの繰り入れをすべて解消するとなると、一人あたり1万円以上の値上げ(一人あたり平均1.6倍)になることを明らかにしました。
国民健康保険はかっては、自営業者、農林水産業で働く方々が多く加入する保険でしたが、今では会社を退職して後期高齢者医療制度に移行する75歳までの方々をはじめ、非正規雇用者が主に加入する制度に「変容」。また国費の投入額が30年前と比較すると、その額は半分程度になっています。したがって、保険料上昇抑制のために、市区町村が独自の繰り入れをして支えている状況です。一方で加入者の多くは低収入でありながら、高額な国保料を課せら得る内容になっています(国保の構造的矛盾)。
わが国において国民皆保険制度がスタートして以来、保険証1枚で日本全国どの医療機関においても診療を受診することができる、世界に冠たる素晴らしい制度です。「同盟国」といわれるアメリカは、民間保険制度になっており、貧困世帯は病院にかかることが困難な社会になっていることを考えると、どうしてもこの国保制度を守ること。あわせて貧困世帯については低額な保険料にすることが、わが国の社会を安定させていくために、どうしても必要だと私は思います。共産党議員団は引き続き、国民運動といったで国会、地方議会でも論戦し、国民の命綱、国保制度発展のために頑張る決意です。
結城亮(結城 りょう)


