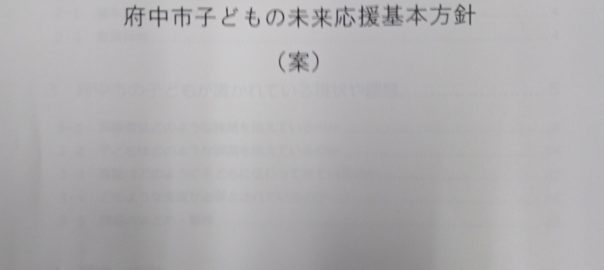19年第1回 結城りょうは、府中市議会一般質問で「中小企業・小規模企業振興策」を府中市に求めます

2月25日から開会する2019年度第1回目の府中市議会定例会ですが、一般質問で私は中小企業・小規模企業振興策の今後の市のあるべき戦略について取り上げる予定です。これは12月の東京都議会において、中小企業・小規模企業振興条例が制定されたことをうけて、府中市においても積極的な中小企業対策を求めるものです。
国も1999年に中小企業基本法を改定し、中小企業を「保護・育成」の対象から、「選別・淘汰」の対象にしましたが、2010年には中小企業憲章の閣議決定、2014年には小規模企業振興基本法を制定するなど、小規模企業の育成支援に舵を切り返しています。
府中市には大企業も立地され、⼤企業(従業者200 ⼈以上)の製造品出荷額が、全体の80%以上を占めている状況で、他市とは違った条件があります。
しかし大企業がもし府中市から撤退するという事態にでもなれば、これは大変不安要素となるわけです。そこで私は、府中市においても将来、積極的な行政戦略のひとつとして、中小・小規模企業育成策を打ち出すことは、市の街づくりの発展と市民生活の向上にも大いに貢献するものと思いました。
今回の質疑は市における、今後の中小・小規模企業育成の大きな方向性を質疑する内容となると思います。私にとっても、この市内中小業者の育成と地域経済発展の施策については、ぜひ今後もライフワークにしていきたいと考えています。
結城亮(結城りょう)