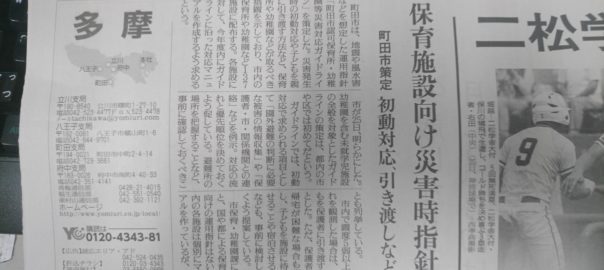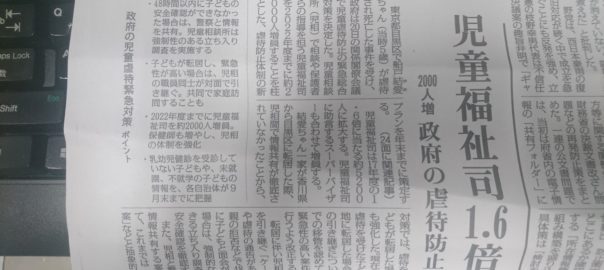民家の危険な塀を撤去補助・・あきる野市、新設の塀も対象
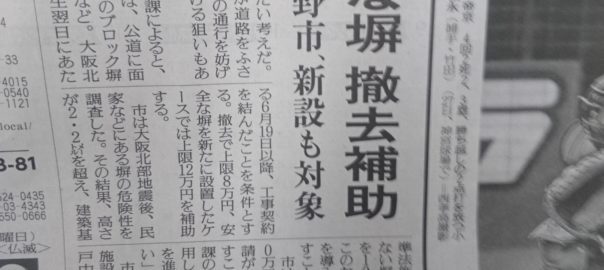
【読売新聞多摩版の報道から】
昨日(28日)の読売新聞多摩版では、あきる野市は倒壊の恐れのある個人所有の塀を対象に、撤去や新設費用を補助する制度を導入し、27日から申請の受付をスタートしたとあります。記事では「市の地域防災課によると、補助の対象は、公道に面した個人所有のブロック塀やレンガ塀など。大阪北部地震の発生翌日にあたる6月19日以降、工事契約を結んだことを条件とする。撤去で上限8万円、安全な塀を新たに設置したケースでは上限12万円を補助する」とあります。また「市は関連予算として500万円を確保しており、申請が多かった場合は積み増しすることも検討している」とのことです。「同課の担当者は『補助金を活用して危険な塀の建て替えを進め、災害に備えてほしい』」としています。
先日の大阪北部地震では、学校のブロック塀が倒壊して女児児童が亡くなるということがあり、各自治体も学校のブロック塀や万年塀の耐震補強を行っていますが、民家の塀に対するこうした対策も急がれるところだと思います。府中市の民家の塀も耐震基準に満たないものが相当数あるものと思われます。市は市内小中学校の塀については緊急策を講じていますが、民家についても早急に対策を講じるよう、要望したいと思います。
結城亮(結城りょう)