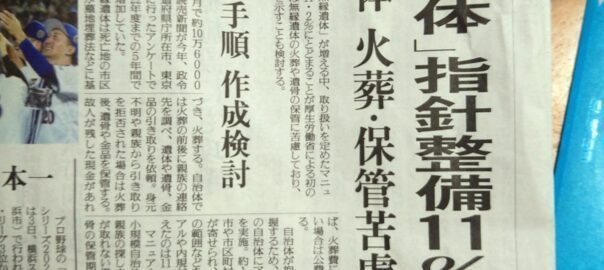府中市議会議員(無党派無所属)の ゆうきりょう です。
★無縁遺体が増加、都内23区でも5年間で3割増へ
今朝の読売新聞一面に、死後に引き取り手のない「無縁遺体」が増えていることで、「取り扱いを定めたマニュアルや内規がある自治体は、11.2%にとどまることが厚労省による初の実態調査でわかった」とあります。「自治体は無縁遺体の火葬や遺骨の保管に苦慮しており、厚労省は今後、統一的な手順を示すことも検討する」とあります。
この記事にもありますが、引き取り手がない無縁遺体は、独居高齢者や親族関係の希薄化にともない、引き取り拒否の増加で増えています。「総務省調査では、2018年から21年で約10万6千人」で、「東京都23区で行ったアンケートでは、22年度までの5年間で3割増加」したそうです。
★身元不明、親族の受け取り拒否が理由、自治体ごとに統一マニュアル作成を指導(厚労省)
記事では「無縁遺体は死亡地の市区町村が墓地埋葬法などにもとづき、火葬する」とし、「自治体では火葬の前後に親族の連絡先を調べ、遺体や遺骨、金品の引き取りを依頼、身元不明や親族から引き取りを拒否された場合は、火葬後、遺骨や金品を保管する」とし、「故人が残した現金があれば、火葬費にあてるが、ない場合は公費で支出している」とのことです。
また記事によると、「約1100の政令市、市区町村へのアンケート結果によると、「マニュアルや内規があるのは、11.2%」だったとし、マニュアルがないのは小規模自治体に多かったそうです。一部自治体へのヒアリングによると「火葬の立ち合いや連絡先を調査する負担の大きさ、遺骨の保管場所の不足を訴える声があがった」「自治体に任せれば低額で火葬してもらえると誤解している意見も出た」そうです。こうした状況を鑑み、厚労省は今後、統一的な指針の作成を自治体に促すとしています。
★独居高齢者が162万人(1990年)から2040人には1000万人超へ
記事では「内閣府によると、1990年に162万人だった独居高齢者は、2020年に671万人、40年には1000万人超になると推計」しているそうです。先日の読売新聞に政府が、身寄りのない高齢者の支援を本格化するとの報道がありました。記事では「65歳以上の単身世帯が増加するなか、身元保証などをめぐるトラブルが相次いでいるため」とし、省庁横断で進めるとあります。
★政府が独居高齢者の身元保証の支援を
また昨年8月の読売新聞の記事では、岸田総理(当時)は独居高齢者が増えている問題で、先進的な取り組みをしている豊島区を訪問、意見交換をしたそうです。「首相は『安心して民間事業者によるサポートを受けることができる仕組み作りを検討する』」とし、高齢者の身元保証代行サービスの普及に取り組むことを強調されたとしています。記事によると、2020年の国勢調査では65歳以上の単身世帯は672万世帯でこの20年間で倍増したが、政府は実態把握が不十分であったとし、総務省が実施した身元保証代行サービスの調査結果によると「事業者の約8割が契約時に重要事項説明書を作成せず、解約時の返金や死後の寄附、遺贈に関するトラブルが発生している実態がある」とのことです。
高齢者の身元保証に関する相談は以前、私にも寄せられたことがあり、今後独居高齢者が増えることが予想すると、すぐにでも実施すべき施策だと思います。とくに住まい確保の時には必要なことであり、高齢者一人ひとりの生活を守る視点から、ぜひ国と自治体が一体で取り組むことを期待したいものです。(府中市議会議員 ゆうきりょう)
※府中市議会議員 ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp