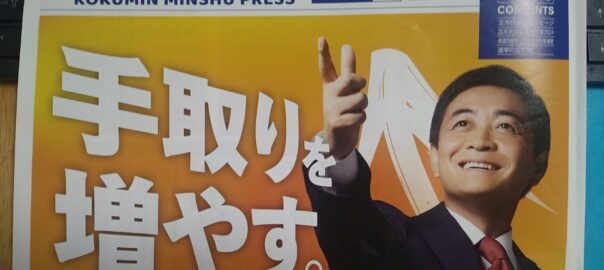府中市議会議員(改革保守系無所属)の ゆうきりょう です。
三井不動産のHPニュースにおいて、同社が西武多摩川線多磨駅前の都市整備用地を活用して、商業施設の開設を計画している件について、新たな情報を提供されているので、以下掲載させていただきます。
★MFLみらいパートナーズが土地・建物の一部を三井不動産より取得
三井不動産株式会社(所在:東京都中央区、代表取締役社長:植田 俊、以下「三井不動産」)とSMFLみらいパートナーズ株式会社(所在:東京都千代田区、代表取締役社長:上田 明、以下「SMFLみらいパートナーズ」)は、かねてより検討を進めてきた「(仮称)府中市朝日町商業施設計画」について土地受益権売買契約を締結いたしましたのでお知らせします。
今後、三井不動産が商業施設の着工に向けて開発準備に着手します。建物竣工後は、SMFLみらいパートナーズが土地・建物の一部を三井不動産より取得し、三井不動産とSMFLみらいパートナーズの2社による保有・運営を予定しています。 計画地は、西武鉄道多摩川線「多磨」駅至近で、北側に東京都道14号新宿国立線(東八道路)、南側に国道20号線(甲州街道)があり、交通利便性の高い立地となっています。
物販・サービス・飲食機能を集積し、スポーツ・エンターテインメントの要素も取り入れた大型商業施設を計画することで、周辺地域の社会・経済活動の活性化、地域住民の生活利便性の向上に寄与するべく努めてまいります。(以上、三井不動産のニュースより)
★商業施設開設にともなう住民説明会が2回開催される
府中市内の北東地域の中心地となる多磨駅前の街づくりのあり方について、今回の三井不動産による商業施設の開設は、画期的なものとなります。私も近隣にある東京外語大学の事務局の方と懇談もし、要望も伺いました。住民の方々からのご要望について、今後も広く伺い、また府中市選出の都議会議員の先生にもご協力いただきながら、多磨駅前の街づくりの発展のために取り組んでいきます。
そこで、三井不動産による商業施設の開設については、今年の3月に住民説明会が開催されました。私は3月25日の説明会に参加してきましたが、以下大きく5つの視点から質疑の内容をまとめましたので、2回にわけて再度、掲載します(その1)。
1,商業施設の駐車場と客の出入り口の課題について
①立体駐車場入り口・・朝日町通り沿い1ヶ所、スタジアム通り沿い1ヶ所、多磨駅東通り沿い1ケ所 人見街道沿いは平面駐車の出口を予定している。
②お客様出入り口・・朝日町通り沿い1ヶ所、スタジアム通り沿い1ヶ所、多磨駅東通り沿い1ケ所を予定している。
③駐車場台数の1650台という数字はまだ決定した数字ではない
2,人見街道との問題について
質問①朝夕、またお彼岸次期は人見街道が渋滞するが、どう考えているか?
●回答・・開業後の人見街道の交差点の渋滞問題はどうするのか・・市、警察との間でどのルートに誘導するべきか、協議をしていく
質問②・・北側、人見街道沿いに自主管理公園があるが?
●回答・・大規模商業施設を建設する際、面積の6%は公園にすることが決まっている。また人見街道沿いに面した位置に作る予定となった理由については、人見街道の歩道は狭いので街道沿いの公園を設けることで、少しでも歩行者が歩きやすい箇所、面積を確保したい考えもあった。また人見街道沿いに車の入り口をつくることはよくないと判断した。
質問③・・人見街道沿いの電柱地中化について促進してほしいが、どう考えているのか?
●回答・・人見街道の無電柱化は望ましいが、事業者だけで進められないので市や電力会社と協議していきたい。
3,住民との協議、話し合い、説明会などについて
質問①近隣の方々との協議についてはどう考えているのか?
●回答・・今日も土地利用構想の段階で説明会を開催した。この後も何度か適切な時期に開催をしたい。次期は未定。
質問②東京外大との話し合いはするのか?
●回答・・今、特別に何か予定してはいないが、今後意見を聞きながら対応したい。
質問③「商業施設計画準備室」へとどいた市民からの意見は、個々へ返されるのか
●回答・・個別に回答することはできないが、いただいた声を拝聴し、生かしていきたい。
質問④・・今後の説明会の予定は?
●回答・・事業の進捗とあわせ適切な時期に実施したい。まずは7月の土地取引の成立をえて、いくつかの案件の手続きをふまえ、行政機関と協議するなかで、再度、説明会を設けたい。
質問⑤パブコメみたいなものをしてほしい
●回答・・準備室を設けているので、ぜひご意見を寄せてほしい
★(仮称)府中市朝日町商業施設計画準備室 問い合わせ先・・担当、高木、矢野、電話03-6696-7071 月~金 (土日、祝日除く 9時~18時)
※府中市議会議員 ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp