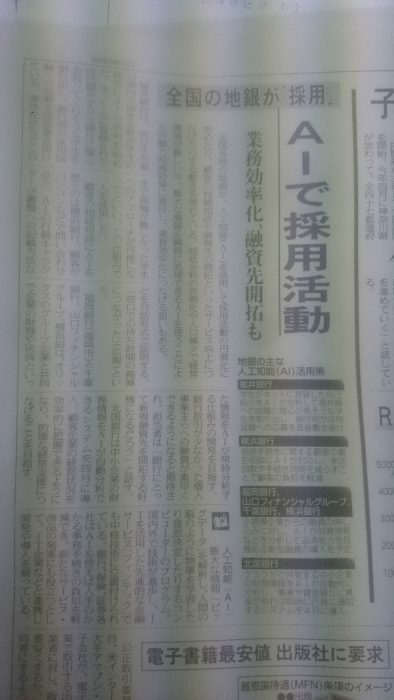浅間町、基地跡地留保地の利用計画の検討委員会がこの秋にも発足します
府中市は平成31年度中に、浅間町に広がる15.5へクタールの米軍基地跡地留保地の利用計画を決定しています。そこで浅間町在住の住民の方より、この留保地活用はどうあるべきか寄稿いただきましたので、以下ご紹介します。
「(留保地活用の)『素案』が平成29年3月に決まりましたが、具体的なことは白紙です。『素案』の確定に際し市は周辺住民からの要望の強い『小金井街道の歩道部分の拡幅』を利用計画に先立ち国と協議することを言明しました。狭い歩道部分に多くの電柱が立ち歩きにくい状態です。利用する近隣住民の意見を聴いたうえで具体案をもって国との協議に入る必要があります。
また『素案』には跡地利用に関する住民の要求がアンケート結果も示されており、この民意を歪めることなく利用計画を検討するよう期待します。どのような利用する場合にも大きなネックになっている『通信塔の撤去』をあらためて関係機関に求めることも大切です。更に、原野化して貴重な生態系が形成されていることにも注目し、複雑な経過を辿って成立したな生態系で保護すべきものにも配慮してきめ細かい対処を望むものです。民間利用される区域にマンション建設を安易に容認することになれば、近隣への影響、景観、保育・教育環境全体への配慮なしには大きな問題を生みかねません。府中市民の重大な関心事ととらえ注目していきましょう」。