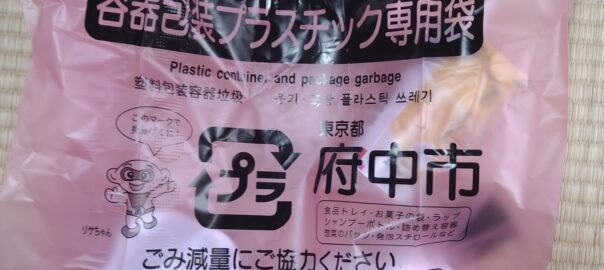府中市 災害時避難所対策の拡充・・防災用モビリティトイレを購入 東京都が雑魚寝解消など避難所対策で新指針

府中市議会議員(改革保守系無所属)の ゆうきりょう です。
昨日の読売新聞多摩版に現在開会中の東京都議会において、小池都知事は「相次ぐ自然災害を受けて、都の防災施策について、避難所運営で新指針」「雑魚寝解消などをなくすべきだ」との答弁をしたと報じています。
★雑魚寝解消、ペットの同行避難など、避難所改善で新指針(小池都知事)
同記事によると、「小池知事は『安心して避難生活を送れるよう、改善に取り組む』と答え、そのうえで、雑魚寝の解消や温かい食事の提供、ペットの同行避難などを盛り込んだ新たな避難所の運営指針を、年度内に策定する方針を表明した」とのことです(質疑をしたのは、都民ファーストの会、森村都議)。
また小池知事は、補正予算案で災害ごみを運搬するための鉄道コンテナ100基の製造費を計上したことを説明、「今月21日の能登半島北部の記録的大雨に触れ、『都が先頭に立って、区市町村とともに支援に取り組む』と述べ、今回の大雨で発生した災害ごみも、都として受け入れる意向を明らかにした」とのことです。
★府中市が補正予算で防災用モビリティトイレ車両を購入、今年度からは自動ラップ式トイレも文化センターに配置へ
府中市議会においても、現在開会中の第3回定例会において、令和7年度 26,548千円(債務負担行為)を計上、「災害発生時のトイレ環境を整備するため、防災用モビリティトイレ車両を購入するもの」として、「防災用モビリティトイレ車両購入事業」を計上しています。
また府中市では今年度予算のなかに、災害時の避難所において、安心してトイレを利用できる環境の整備のための、自動ラップ式トイレの購入費用、94台を導入。小中学校、文化センターなど47ヶ所に導入もしています。読売記事では、自動ラップ式トイレについて「洋式便座に設置された専用袋に用を足した後、薬剤で汚物を固め、自動的に密閉する仕組み。停電時でも使えるように、あわせて非常用発電機も購入、費用は計約3640万円を見込む」とあります。「市の防災危機管理課によると、災害時の避難所では、汚れたトイレの利用をやがって我慢し、便秘やぼうこう炎などの健康被害を起こす人がいる」「トイレの利用は不可欠なため、衛生的な自動ラップ式トイレを導入することとした」としています。
災害関連で体調を悪化させる原因のひとつに、排便などの問題がありますが、各地の避難所には、こうしたラップ式トイレは必須のものです。ぜひ今後配備の増設を求めたいと思います。
★防災資材等整備費・・災害発生時に、多くの避難者が衛生的かつ安心して使用することができるトイレ環境を整備するため、自動ラップ式トイレを購入し、各避難所に配備する。予算・・3642万円
※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情など、また新型コロナ関係でのご要望などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp