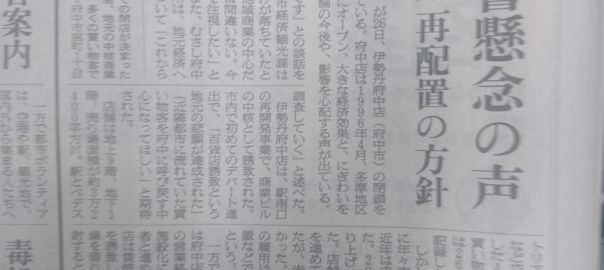府中市でも中小企業・小規模事業対策条例の制定と支援策の強化を

先日は東京都が中小企業対策条例が検討されていることをブログに書きましたが、6月市議会の一般質問で他会党派の議員の方が、この問題で質疑をされていました。主には府中市が発注する仕事に関して、指名競争入札における市内業者のあつかい、市による中小零細企業の支援策、また市独自に条例制定をする考えなどについてのやりとりでした。
私もこの問題には大変関心をもっていました。具体的には中小零細の事業主にとっては、社会保険料の負担が重荷になっています。国も最近では法人に対して、源泉徴収している社員については原則、社会保険に加入させろという行政指導を強めていますが、現実にその負担ができないのが現実です。この点をどうクリアするのかが問われると思います。
また脱サラをした方が小規模事業を起こして、自らの人生と仕事に生きがいを見出すこと方々への支援策も検討するべきだと思います。
こうした点からも自治体独自の中小零細企業を支援する独自の条例が必要だと思います。府中市に在住して府中市で自ら起業する方々を支援することは、地域経済活性化の点でも必ずやいかされてくると思います。私も様々な面から、研究して一度議会でも取り上げたいと思います。
結城亮(結城りょう)