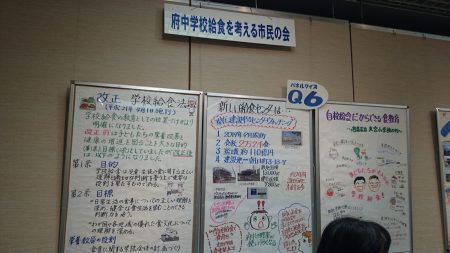若者の声、政治に届くか・・国会で超党派35人の議員連盟発足

【東京新聞の報道から・・若者の政治参加促進を】
今朝(25日)の東京新聞26、27面に、超党派の国会議員が「若者政策推進議員連盟」を発足させ、インターネット投票の導入や被選挙権の年齢引き下げを実現して、若者の政治参加を促進させようという記事が掲載されています。また記事では「(若者の)政治意識を高めようにも、教育現場では政治的中立性が求められているなど課題も多い」とあります。日本では2016年の参議院選挙から選挙権が20歳から18歳に引き下げられ、「昨年の衆院選では、全体の投票率は53.7%、20代は33.9%と各世代で最低、10代の投票率も40.5%だった。ちなみに24年前の20代は47.5%、50年前は66.7%だ」と記事にはあります。
【スウェーデンでは学校現場で政党議員による政治討論会を開催】
私も衆院選挙、市議選と2回の候補者を経験しましたが、確かに10代、20代の選挙公約というのは掲げていませんでした。将来の日本社会を担う青年層こそ、本当は公約の充実が必要だと思うのですが、そうした傾向は日本の政界ではまだ希薄だと思います。いくら若者に「選挙に行こう」と呼びかけても、主権者たるその心に響かなければ、彼らは投票には行かないでしょう。
またこの東京新聞の記事では20代の投票率が80%超という、スウェーデンの取り組みを紹介し、若者の政策提言を政府も団体支援しているというものです。またスウェーデンの取り組みで興味をひいたのは、「スウェーデンの学校の政治的活動を制限する規定はなく、各政党の議員を平等に学校に招く政治討論会も開かれている」とのことです。およそ日本の学校現場では考えられない取り組みです。
若者だけではなく国民一般に言えると思いますが、自分の投票行動が政治を変えたという経験があって、初めて政治参加、投票行為という積極的行動にでるのではないでしょうか。私も朝、夕方での駅頭、街頭でのあいさつを通じて、通学下校途中の高校生、中学生と遭遇します。そうした彼らに対して、私の訴えが少しでも政治に興味をもち、将来、自分が日本の政治を良くしようという志をもつ、若者が出てきてくれることを願っています。この若者の政治参加の問題は、また今後ブログでも取り上げたいと思います。
結城亮(結城りょう)