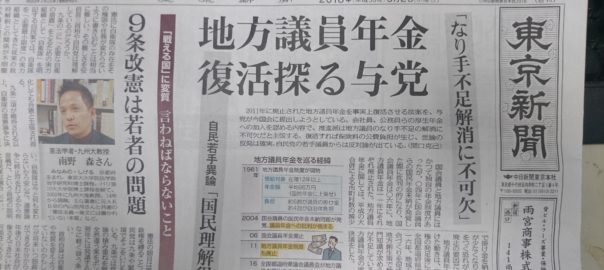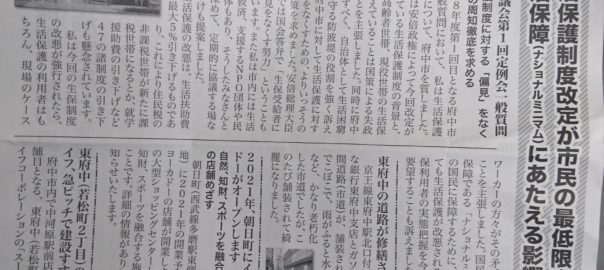「若者の○○離れ」ではなく、「お金の若者離れ」こそ問題だ
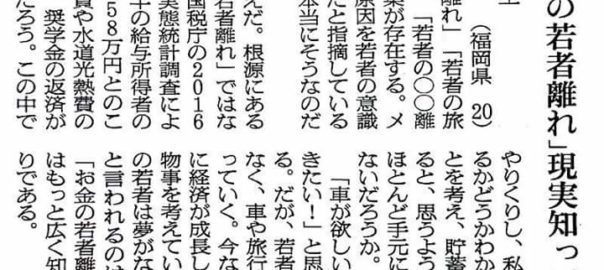
【右肩上がりの経済成長の時代とは真逆の今日が原因】
昨日(5日)の朝日新聞投稿欄に、20歳の大学生の投稿が掲載され、大変興味深い内容です。そのなかでは「若者の車離れ」「若者の旅行離れ」などという言葉が存在するが、メディアはその原因を若者の意識の低下のせいだと指摘しているが、果たしてそうだろうか」と疑問を呈し、投稿者は「根源にあるのは『お金の若者離れ』ではないだろうか。国税庁の2016年分民間給与実態統計調査によれば、20代前半の給与所得者の平均年収は258万円とのこと。月々の家賃や水道光熱費の支払いに加え、奨学金(大学のローン)の返済がある人もいるだろう。このなかでやりくりし、私たちに支払われるかどうかわからない年金のことを考え、貯蓄に回す分を含めると、思うように使えるお金はほとんど手元に残らないのではないだろうか」と主張されています。「今なお、右肩上がりに経済が成長した時代の感覚で物事を考えている人から、『最近の若者は夢がない。欲がない』と言われるのはうんざりだ」としています。
【結城りょうの視点・・雇用、所得、社会保障など政治の責任で社会の再構築を】
この投稿は現在の日本社会の構造を考えるうえで、示唆に富む内容ではないでしょうか。現在は5600万強の雇用労働者のうち、40%が非正規雇用。雇用と年収が安定せず、さらにはせっかく学校を卒業して正社員として就職できても、そこはブラック企業だったということは今日では、もはや普通のことです。社会経済環境では、インフレと年々引きあがる税や社会保険料などの国民負担は増すばかりです。そして大学時代の奨学金ローンの返済が40歳から50歳まで続くわけです。たしかにこれでまともな結婚生活ができるのか、自動車の購入や、旅行などを「優雅」にできる社会かといえば、とてもそうだとは言えないでしょう。
今の日本社会、日本経済と健全に立て直すには、非正規雇用から安定して働ける正規雇用が当然の社会にもう一度立て直すこと、勤労者の可処分所得を増やして、消費購買力を向上させること。医療、年金などのセーフティーネットを強固な制度に再構築して、安心して働ける社会を保障すること。そうすれば必然的に消費も上向き、結婚して家庭をもつ人たちが増えるでしょう。日本の企業は1995年以降、「新日本的経営」を思考した経営スタイルになり、行政や政治もそれを後押してきました。ここを政治の責任で改める以外に、この投稿者の悩みに応えることはできないのではないでしょうか。ちなみに95年当時、「新日本的経営」を一番主張されていた経営者の方も、今日では一定の「反省」をしています※。
※昨年12月17日付ブログ「宮内義彦氏(オリックス・チェアマン)が、今日の株主優先の経営手法と、資本主義のあり方を反省(朝日新聞)」参照
結城りょう