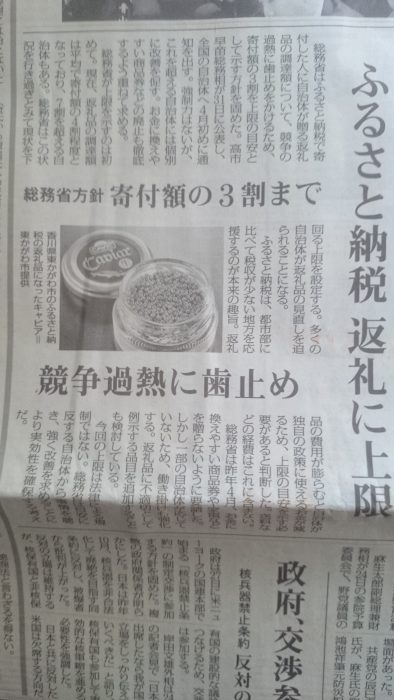生活保護受給者のパチンコを調査、厚労省が指導状況や不正受給など実態把握へ
先日(4日)、厚労省が生保受給者のギャンブルの実態調査を行う予定との記事をを、赤旗日刊紙や商業新聞(産経など)が報じました。それによれば(産経記事)、「生活保護受給者がパチンコや競馬などの公営ギャンブルをしている事例や、自治体の指導状況について、厚生労働省が実態調査を始めたことが3日、分かった。日本維新の会の議員が1月に衆院予算委員会で調査を求め、塩崎恭久厚労相が実態を把握する方針を示していた。厚労省は各地の福祉事務所に回答を求める通知を3月に都道府県などに送付。パチンコやギャンブル、宝くじなどについて、過去1年間に受給者を指導した件数、パチンコなどで得た収入を申告しなかった不正受給の件数などを聞いている。生活保護法にパチンコなどを禁止する規定はないが、過剰な場合にはケースワーカーが指導することがある。大分県別府市と中津市がパチンコをしていた受給者の保護費を一部停止するなどしたケースでは、厚労省が昨年『不適切』と指摘し、両市が撤回した」と報じています。
以前から私も知り合いから「生保受給者がパチンコなど、ギャンブルをしている人もいる」という話を聞くことがあります。私は以前、生活困窮者を救済する運動団体の方にこのあたりのことを伺ったところ、「生活保護受給者のなかで案外多いのは、ギャンブルによって身を破滅させた方々だ。恐らく、ギャンブル依存症になって自己破産して、生活に困窮したのではないか」と語っていました。私もそう思います。単に娯楽でパチンコに興じている方もいるでしょうが、依存症に陥っている方が多いのも事実ではないでしょうか。また赤旗でも報じていますが、今回の調査が「人権侵害につながる恐れ」のある可能性もあります。やはり、依存症であれば治療が必要です。私も今後、現場の実態を調べ、よりよい方策を考えたいと思います。