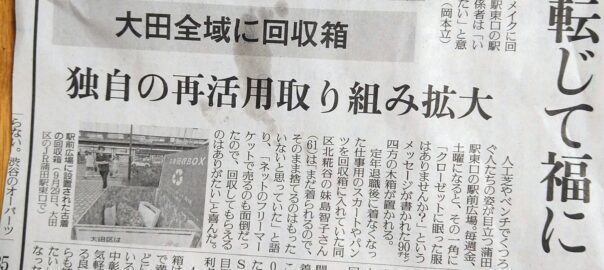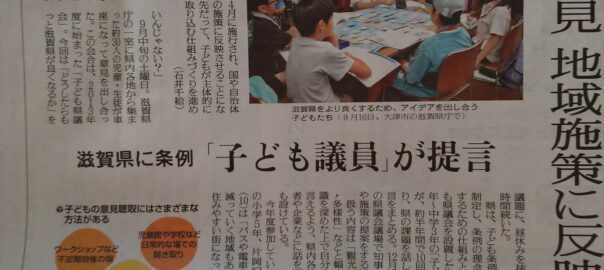(府中市)高齢者介護に配食、家事、通院などの日常生活を民間企業との連携で、福祉サービスの拡充を

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。
★高齢者向け民間業者のサービス情報を集約、地域包括支援センターがサービス利用につなげる
先日の読売新聞で、政府は高齢者の日常生活を支えるために、介護保険サービス以外の民間サービスを利用しやすい新たな仕組みをつくるとしています。記事では「市区町村ごとに訪問理美容、配食サービスなどの民間業者の情報を集約し、『地域包括支援センター』が高齢者の利用につなげる」とし、介護する家族の心労を軽減することが狙いとあります。
★全国でモデル事業を展開、先進的な愛知県豊明市の取り組み
記事によると政府は全国の10の自治体でモデル事業を始め、地域ごとに民間事業者の参加を募り、配食サービス業者や買い物、掃除などの家事代行業者、食品や日用品を宅配するスーパー、通院サポートするタクシーなど交通事業者など、様々な事業者に加わってもらう計画です。
記事では「政府(経産省)が参考しているのが愛知県豊明市の取り組みで、同市では社会福祉協議会がつかんだ地域の高齢者のニーズを基に、2016年度以降、市内や近隣の温泉施設、スーパー、スポーツクラブなどに声をかけ、18の事業者と協定を締結。連携しながら介護予防や食料品の個別配達などのサービスを提供し、高齢者の暮らしをサポートする」としています。
この豊明市の取り組みは大変興味深いものです。私も以前から社会福祉協議会と地域包括支援センターが連携しながら、地域住民、高齢者とその家族のニーズをつかみ行政サービスにつなげることが重要だと思っていました。
今後、行政サービスだけでは充足できない高齢者向け福祉サービスについて、民間業者の活力を生かすことで、高齢者福祉サービスを補完していくことは重要です。ぜひ一度、豊明市の担当者の話も伺い、議会でも取り上げたいと思います。
※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情など、また新型コロナ関係でのご要望などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp
★市政の話題など、ブログ毎日更新 検索⇒ゆうきりょう