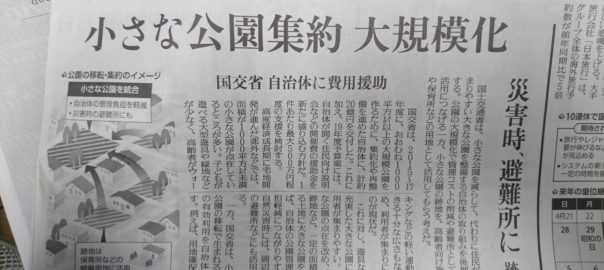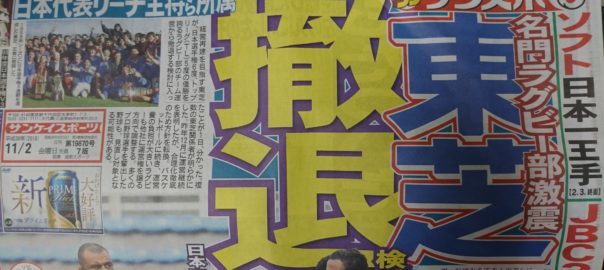府中市の保育所への19年度(平成31年度)申込みについてのお知らせ

府中市では平成31年度4月1日からの保育所等への入所・転所の申込み及び子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請を次のとおり受付けていますので、以下お知らせいたします(市のホームページから抜粋)。
①受付期間・場所
平成30年11月12日(月曜日)から11月22日(木曜日)午前9時から午後5時まで
:11月17日(土曜日)、11月18日(日曜日)は午前9時から午前11時半まで受付けます。
:11月19日(月曜日)、11月20日(火曜日)は午前9時から午後7時まで受付けます。
:いずれの日も午前11時半から午後1時半は受付けておりません。
②受付会場・・市役所北庁舎3階第4会議室
:平成31年2月3日までに出産予定の方も保育所等の申込みができますので、受付期間内にお申込みください。なお、平成31年2月4日以降に出生の場合は4月1日付入所内定していても取消しとなります。
:受入予定数は10月26日(金曜日)に公開予定です。
③対象者
心身ともに健康で集団保育が可能な児童で、保護者が就労(1か月48時間以上)や病気等の理由により、児童を家庭で保育できない場合
:集団保育を経験させたいといった理由のみでは該当しません。
:利用調整の対象者は、保育を必要とする認定(2号又は3号認定)を受けている児童(予定を含む)のみとなります。
:原則、府中市の住民基本台帳に登録されている児童
④府中市以外からお申込みの方へ
平成31年3月31日までに府中市への転入予定がある方については、現在お住まいの市区町村へ府中市の受付期限までに書類が届くようにお申込みください。申込書以外の書類(認定に必要な書類等)については必ず府中市の書式を使用してください。府中市以外の書式で申込みをされた場合、利用調整において不利になることや、支給認定および利用調整ができない場合があります。申込書類は、下記の提出書類のほか転入先の転入に関する誓約書、不動産契約書等の写しも必要となります。
なお、0から2歳児クラスで転入予定のない(転入先住所が未確定の場合を含む)方の受付けはできません。
また、3歳児クラス以上については、転入予定のない(転入先住所が未確定の場合を含む)方でも2次募集から受付けをすることができますが、利用調整においては府中市民を優先します。
注記:2次募集の受付期間は平成30年11月26日(月曜日)から平成31年2月15日(金曜日)(土日祝日及び年末年始を除く)午前8時半~午後5時15分
注記:平成31年2月16日(土曜日)と2月17日(日曜日)のみは午前9時から正午まで受付けます。
⑤提出書類
決められた用紙、就労など保育要件確認のための書類、チェックシートなど。
「平成31度保育所等申込みのしおり」、申込書などの提出書類は、次の施設、窓口に用意しています。また、このページからダウンロードできます。
- 市役所東庁舎5階保育支援課
- 市立保育所・私立保育園・地域型保育事業
- 市政情報センター
- 子ども家庭支援センター「たっち」
- スクエア21・女性センター
- 詳細の問い合わせ先・・府中市 子育て支援課 042-335-4100