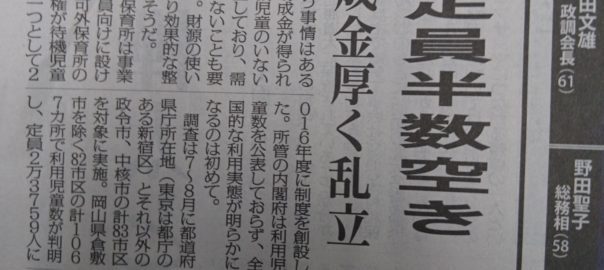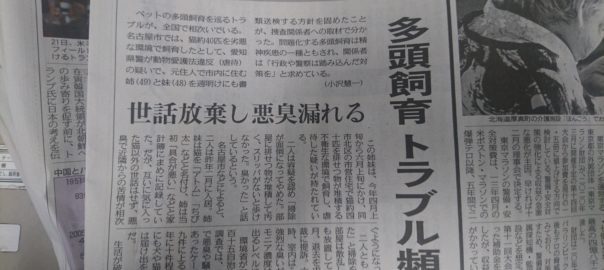若松町2丁目、関野原自治会で防災訓練

9月は防災訓練を行う自治会が多いなか、9月22日(土)午前10時30分から、府中市の若松町2丁目の関野原自治会で防災訓練を行いました。私はこの自治会の防災担当の役員をしているので主催者でもありました。
当日は自治会の住民の方30人ほどが集まり、震度7の起震車体験と消火器の使い方の訓練をしました。震度7は地面から突き上げるような大きな揺れと、横に大きく揺れる内容です。「もし自分が都心にでもいたら命はない」と思えるような揺れです。消火器については大変簡単に操作ができます。
訓練の最後には府中消防署の方による講話をしていただき、地震や火災の際の心得について話をしていただきました。地震の際は家具が倒れてその犠牲になる方が多いとのことで、家具転倒防止金具の取り付けが大変重要との話をされていました。こうした防災活動は9月中に、多くの自治会で防災訓練が行われているようです。私もこうした体験を市政への要望としてつなげていきたいと思っています。
結城亮(結城りょう)