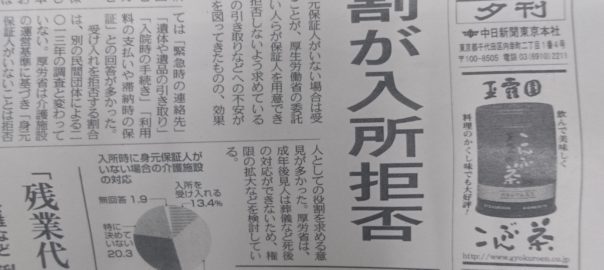ひとり暮らし高齢者などへの訪問支援事業を区内全域で開始・・練馬区
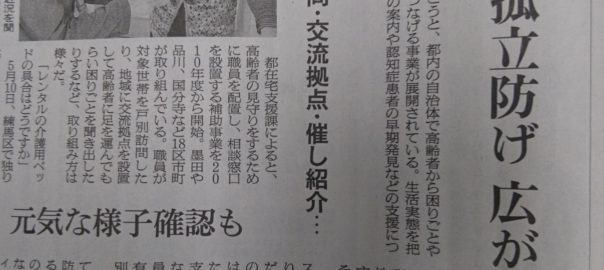
【訪問支援事業の対象者2万人を民生委員の調査などから整理、すべての包括地域センターに2人ずつの専従訪問支援を配置・・練馬区高齢者支援課】
先日私の6月29日付ブログで朝日新聞多摩版の記事「自治体が高齢者世帯に戸別訪問を介護保険の申請などを聞き出す取り組み」を紹介しましたが、本日、この事業を実施している練馬区の高齢者支援課に話を伺ってきました。練馬区では、今年の4月から区内全域において高齢者世帯に対する「訪問支援事業」をスタートしました。対象となるのは、区内のひとり暮らし高齢者および、高齢者のみ世帯で、介護保険を受給していない高齢者を対象(2万人)としているとのこと。
この事業は、区内25ヶ所の地域包括支援センターの機能強化を目的に検討を開始した経過があり、全ての地域包括センターに社会福祉士など、専門資格をもつ専従の訪問支援員を2人ずつ配置したとのことです。
この支援員の方が訪問時に生活実態を把握し、介護予防事業の案内や、介護サービスの申請など新たな支援につなげることを目的としています。また定期的な訪問が必要な方は、区民ボランティアなどが見守りを行い、認知症昨日低下などを早期に発見できる体制を構築しようというものです。練馬区では昨年、2ヶ所の地域包括支援センターにおいて、この事業をモデル実施しており、地域から孤立していた高齢者夫婦や、近隣とのトラブルを抱えていた高齢者など、生活上の課題を抱えた高齢者を把握して、介護サービスを含めた必要な支援につなぐなどの、高い成果をあげたとの事です。
この事業は東京都の在宅支援課が補助事業として実施しているもので、練馬区のこの事業を活用して、今年度は2億5千万円の予算を組んだとのことです(このうち半分は都の補助金を活用)。
なお対象者2万人の名簿については、地域の民生委員が地域ごとの高齢者世帯の実態調査をしているので、それを行政が整理したとのことです(生活保護受給者については、同区ではケースワーカーのほかに、生活支援員を配置しているので、この見守り制度の対象外とのこと)。
【ぜひ府中市でも実施を要望したい】
練馬区でもこの制度は4月からスタートしたばかりで、詳細の分析は今後になりますが、多くの方々は健康な高齢者の方とのこと。そうした方には、介護予防事業への参加を促すほか、なかには地域でボランティア活動を希望する方もいるとのことで、高齢者を地域社会につないでいくためにも役立つ事業になっているとのことです。担当課長さんの話を伺って、私は大変興味のある事業だと思いました。
ちなみに都に確認したところ、多摩地域でこの事業を実施ているのは、国分寺市、八王子市、三鷹市、青梅市、狛江市、東大和市、武蔵野市、武蔵村山市、多摩市とのこと。まだ府中市は実施していないので、ぜひ一般質問などでも取り上げて、事業の実施を要望したいと考えています。
結城亮(結城りょう)