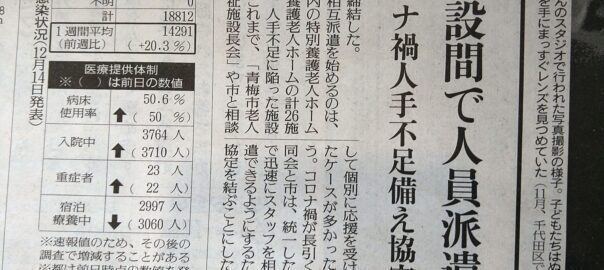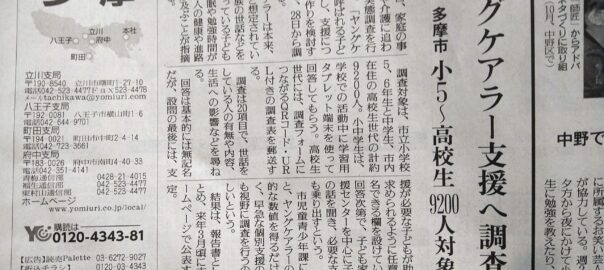府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。市民の方からの要望で、府中市(役所)の障害者雇用率が多摩地域の自治体で最下位であることに対する、ご意見をいただきましので紹介させていただきます。
★民間企業は障害者雇用の促進に頑張っているのに・・
府中市の行政において、一つ心配になっていることがございます。それは、市の障害者雇用率です。府中市の令和4年度の雇用率は1.7%でした。この数値は、多摩の各自治体で最下位です。5年前は0.79%とありえない数字でそのことを猛省して取り組まれていると思っていたのですがたった1.7%で法定雇用率2.6%を達成していないことに愕然しました。
(東京労働局発表 令和4年障害者雇用状況の集計結果⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/newpage_00060.html)
府中市は全国でも指折りの裕福な自治体なので雇用できる体力は十分あるはずです。たまたま市職員採用試験に突破できるだけの力を持った障害者が集まらなかったのかもしれませんが、民間はできるだけ頑張って雇用を進めています。
障害者を雇用することは、障害に起因する課題など色々難しい問題はありますが、障害者が働きやすい環境は、通常の職員にとっても働きやすい環境になることが多いです。職員が生き生きとして働きやすい職場になることは、私たち市民にとっても良い影響が出てくると思います。なお、国は障害者雇用水増し問題を反省して、「障害者活躍推進計画」なるものを策定して、取り組んだ結果、雇用率達成したようです。
★「障害者活躍推進計画」の策定メンバーに、障害者当事者の参画を求めたい
この「障害者活躍推進計画」は障害者当事者が参画して計画策定をしたそうです。厚生労働省から各自治体において「障害者活躍推進計画」を策定するにあたり、障害者当事者にはアンケートなどの聞き取りだけではなく、計画策定に参画するようにという通知を行ないました。 しかし、府中市の障害者活躍推進計画及び策定委員メンバーを見てみる限り、障害者当事者の参画が見当たりません。これでは、雇用率が伸びないことは納得いきます。
府中市は、障害に関する知識の啓蒙を頑張っているようですが、これはこれで頑張っていると評価すべきことです。しかし、民間に障害者雇用の促進をお願いするには、まずは府中市が率先して雇用率を達成してから取り組みを進めるのが筋なのではないかと感じます。
府中市は障害者とは一緒に働きたくないのではないかと思ってしまうこともあります。大変難しい問題ですが、取り上げていただけますようよろしくお願い申し上げます。(以上、市民の方の声より)
※ゆうきりょうの関連ブログ⇒ 障害者雇用水増し・・府中市は法定数の不足が24人、雇用率0.79% – 市民派無所属 府中市議会議員 ゆうきりょう (r-yuuki.jp)
●ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情など、また新型コロナ関係でのご要望などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp