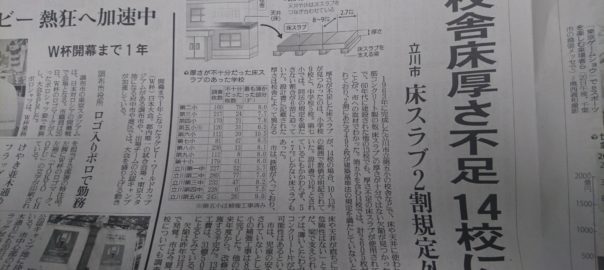東京都の教員不足280人・・都議会共産党の質疑で答弁

【東京民報18年10月7日付記事より】
共産党東京都議団による都議会一般質問で、とくとめ都議が教員不足の現状について質問したところ、都は「4月6日時点で280人の教員不足が生じている」との答弁しました。原因については「教員必要数を推定するための児童、生徒数が増加して、再任用者数が予想を下回ったこと」をあげたとのことです。とくとめ都議は新規採用教員が不足して、校長や副校長らがクラス担任に入らざるえない深刻な事例を紹介し、「先生が足りないことによる学校の負担と子どもたちへの影響ははかりしれない」と主張しました。またとくとめ都議は「教員確保へのブラックと言われる働き方の改善や、教員の定数増と少人数学級の拡大、教員の仕事削減などを井要望し、教員志望の若者を増やす施策について提案しました。
これに対して小池都知事は「教員をめざす若者が、東京の公立学校が魅力あるものとなるよう取り組んでいく」と答弁しました。
私も17年6月議会の一般質問で教員の長時間過重労働問題を取り上げましたが、現場の先生の話を聞くと本当に「絶句」するような忙しさでした。「明日の授業の準備もすることができない」とある先生は嘆いていました。それにしても280人の教員が不足しているというのは、大変な驚きです。
教員不足は結局のところ、教育の質の低下をもたらして、それは日本の未来を担う子どもたちの成長を阻害するものになることでしょう。とくとめ都議の提案は現実可能な提案だと思います。国、都、自治体と一体となった教員不足解消策と教育の質の向上をめざす取り組みについて、今後も議会で取り上げたいと思います。
結城亮(結城りょう)