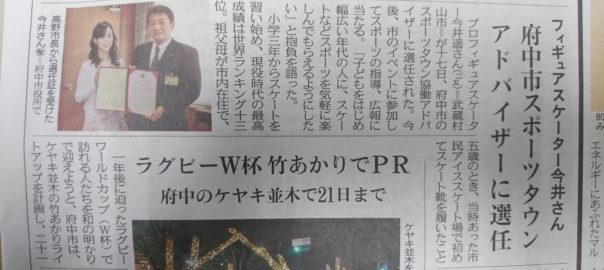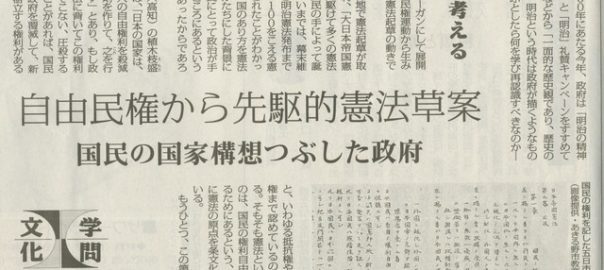西武線多磨駅の自由通路整備と鉄道施設改良の整備計画について、市から報告がありました

11月22日の市議会建設環境委員会において、府中市と西武鉄道(株)が協力して進めている、西武多摩川線多磨駅の東西自由通路の整備と、駅舎の橋上化などの鉄道施設改良について、市から整備計画の報告がありました。
工事期間については、2019年5月から本体工事の着工開始、2020年7月までに本体工事のしゅん工および供用開始がスタート。2020年末までに既存構造物の撤去を予定しています。
★改良後の駅の内容・・駅東西側にエスカレーター設置、地下通路は閉鎖撤去
自由通路は東側通路が幅員6.4メートルから6.7メートル(エスカレーター含む) 、西側通路は幅員4.9メートルから5メートル(エスカレーター含む)。
2階通路は幅員10.5メートル、付帯設備はエレベーター(17人乗り)を2基設置、いずれも「上り」用エスカレーター設置。ほかに駅の事務室、トイレ、窓口、券売機と改札口があります。 1階はプラットホーム(1面)、ちなみに現在ある地下通路は閉鎖撤去とのことです。
私も毎週月曜日に朝6時15分ぐらいから8時まで駅頭に立っていますが、6時代から多磨駅におりる客(警察大学校、東京外語大学の職員や生徒など)が多いのに驚きます。また武蔵境駅行き電車も7時30分から8時ぐらいにかけては、かなりの乗客数です。ただエスカレーターについては東西両側とも上りだけしかないのが、残念です。市の説明では「幅員確保ができないため」とのことです。また都市計画道路も整備されることとあわせて、2021年に大型民間商業施設も建設されることから、多磨駅周辺の街の様子も様変わりするのではないでしょうか。
結城亮(結城りょう)