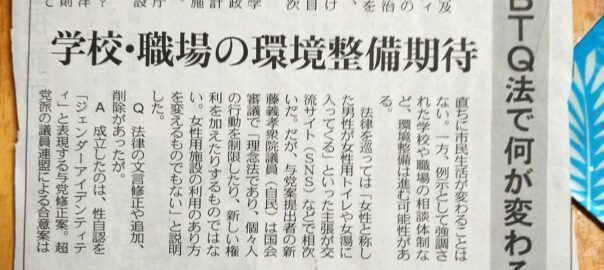(府中市)ふるさと納税を活用して、子どもや若者の居場所確保を・・立川市が運営資金を募る取り組み

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。先日の朝日新聞多摩版に、立川市がふるさと納税を活用し、ひきこもりや不登校になったり、虐待を受けたりした子ども、若者らを守る居場所の運営を寄附で賄う取り組みを始めているとの記事があります。
★若者支援団体を市が財政支援、ふるさと納税を活用、返礼品はなし
目標額は300万で、期限は年末、返礼品はないそうです。記事によると、対象の施設は若者の自立を支援するNPO法人「育て上げネット」が昨年5月に開設したフリースペース「夜のユースセンター」で、毎週土曜の夜、家でも学校でもない第三の居場所として、様々な境遇の若者らが40人以上が集まるそうです。今年3月までにのべ利用者は1000人を超えているとのことです。記事のなかで同法人の理事長は「(新宿、歌舞伎町の)『トー横』に行っていた子どもも安心に過ごせるならと言っている。市からの支援を支えに子どもと信頼関係を築いていきたい」と話されています。
行政によるこうした支援のあり方は、大変参考になるのではないでしょうか。「志」やノウハウはあっても、資金がないばかりに支援策の具体化ができない市民、民間団体の方が多数と思われます。しかしながら、こうした方々にこそ、行政が財政支援をすることなど求められています。
政府は孤独担当大臣も配置し、孤立策防止の施策を実施していますが、自治体の現場ではすでに先取りした施策が多数あるはずです。「誰一人も取り残さない社会」というスローガンをかかげる政治家は多いのですが、その思いを必ず実行あるものにするためにも、立川市のように、ふるさと納税を活用した取り組みは大変意義あるものです。ぜひ府中市においても参考にしてとりあげ、市に要望したいと思います。(府中市議 ゆうきりょう)
※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などお気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp
★市政の話題など毎日ブログ更新中 検索⇒ ゆうきりょう