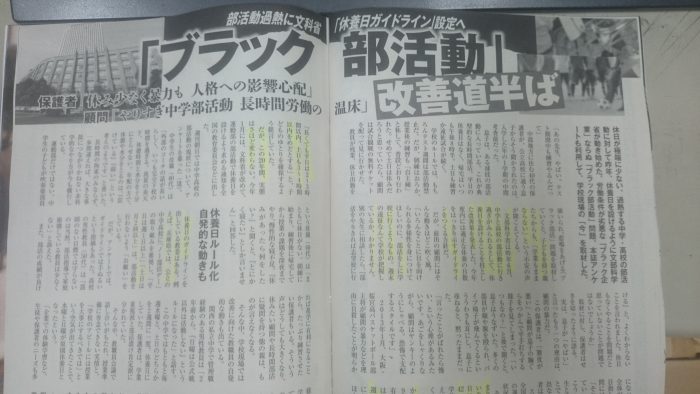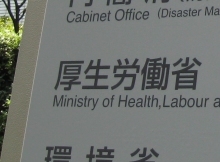「ブラック部活動 改善道半ば、文部省『休日ガイドライン設定へ』」(週刊朝日)
今朝(10日)は京王線東府中駅北口で、からさわ地平 都議予定候補とあいさつ、午前中一般質問の準備聞取りなど。
先日ブログで文科省による全国の教員の勤務実態調査について掲載しましたが、週刊朝日の5月19日号では、見開き2ページで「ブラック部活動 改善道半ば、部活動過熱に文科省『休養日ガイドライン』設定へ」との特集があります。記事では中学校の部活動が過熱し過ぎるあまり、教員の勤務実態がブラック化している現状、また生徒たちの勉強する時間もなくなるような実態についても掲載しています。文科省もこうした実態をつかみ、近くガイドラインを設定すると記事にはあります。記事では部活に時間をとられざるえない親御さんの、悩みの声もとりあげています。以前私は、市内中学校にお子さんを通学させていたという親御さんからも聞いたことがありますが、そのお子さんも運動部に加入していて、帰宅時間が夜8時前後になっていたとのこと。顧問の先生も「熱心」な教員で、運動部は対外試合などで成績が良いものの、お子さんの学業は反比例するように悪くなっていったとのこと。しかし親御さんは、こうした実態を学校に伝えようかと何度も思ったものの、余計なことを指摘したばかりに、子どもの内申書に悪影響を与えたら申し訳ないという思いで我慢されていたと、話を伺ったことがあります。
私も中学時代は野球部でしたが、確かに帰宅するのは通常、夜7時30時前後、勉強は夜9時から、日曜も練習試合などもあり、日々疲れていたように思います。過熱する中学の部活動についても、今後現場の教員から聞き取りなどもしたいと考えています。