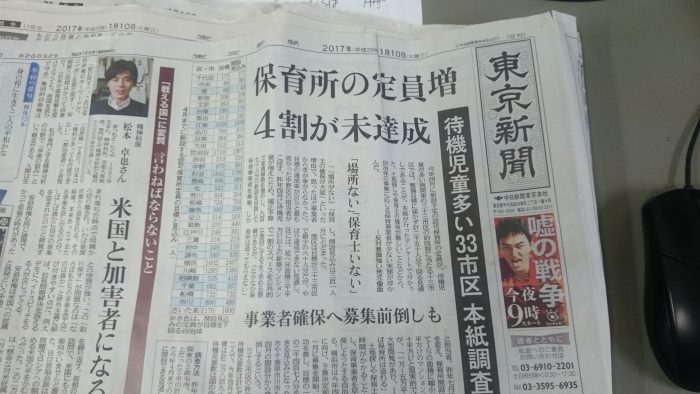東京土建府中国立支部 年間100人実増・・盛大に新春旗びらき開催
昨夜(12日)は、むさし府中青年会議所と東京土建府中国立支部の新年会に参加してきました。青年会議所の新年会は、初めての参加でしたが、40歳までの方々が会員ということもあり、活気を感じました。今後、府中の実業界はじめ、様々な分野でリーダーとなる方々だと思いますので、これからもこうした場に参加したいと思います。
もう一つは、東京土建府中国立支部の新年会です。私は東京土建の事務局に10年間、そのうち3年間は同支部で勤務していたので、とても懐かしく嬉しい思いで参加しました。同支部は、2年連続で100人以上の年間実増を果たす東京土建36支部のうちの1位をいく組合員の増加数の実績をあげています。昨年、東京土建36支部全体で300人の実増のうち、100人の実増成果を府中国立支部があげていることになります。これは驚異的な数字です。東京土建全体で年間、数千人増やした10年前に匹敵する組合員の拡大数を誇る成果です。同支部は、毎年6月に開催している住宅デー運動など、建設産業運動でも実績をあげ、本部からも高い評価をうけています。石村英明委員長は50歳前半の若い委員長で大変よく勉強され、組合員からの信頼も厚い方です。また事務局をまとめている責任者の吉田主任書記が、毎月の組合員拡大に執念を燃やし、事務局が中心となった組合員拡大で毎月の成果をあげています。昨日の新年会に来賓で招かれていた本部役員の方も「組合員さんの笑顔が印象的だ。式典の段取りも大変良く、36支部のなかのトップ3の支部だと思う。年間100人増やすだけの支部だ」と語っていました。私も同じ感想で、良い意味で事務局の「緊張感」を感じました。私も3年間ではありましたが、府中国立支部に貢献できて大変嬉しく思います。東京土建の運動と組織は、地域、行政に多大な影響をあたえる組合です。今後も大いに協力、連携していきたいと思います。