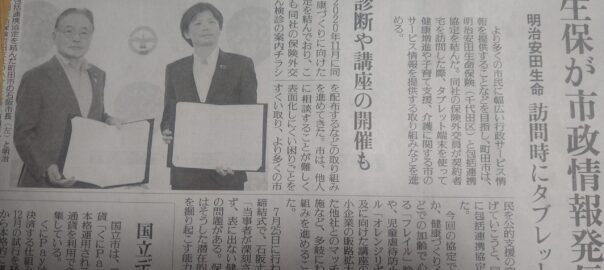府中市 児童発達支援センター こども家庭庁が児童発達支援センターの人材育成強化を方針へ

府中市議会議員(改革保守系無所属)の ゆうきりょう です。
先日の東京新聞に、加藤鮎子こども政策担当大臣が、「障害のある子どもが全国どこでも質の高い支援サービスを受けられるよう、地域で支援の中核を担う児童発達支援センターなどの人材育成の研修を強化する」とし、「研修の体系や実施体制の具体的な検討を進める」との考えを示したと報じています。
この記事では「送迎が必要な障害児のいる共働き家庭など、多様化しているニーズに応じるため『支援の実施状況を把握する』と語った」とあります。また記事にもありますが、児童発達支援センターは、未就学で障害のある子どもを対象にして、日常生活の基本的な動作や必要な知識の指導、集団生活への適応訓練などを行っており、「地域の事業所や保育所と連携して、子どもや家族への支援に取り組んだ場合、障害福祉サービスの報酬が加算される」としています。
★府中にも市の施設と民間による運営の児童発達支援センターが存在
府中市にも今年の4月から、児童発達支援センター「はばたき」(府中市矢崎町1-12)が開設され、①発達に関する相談、②教育相談、③就学や転学相談、④通園、グループ、個別形式による療育支援、⑤保育所や幼稚園など、子どもの所属先に対する支援、⑥教育相談、就学と転学相談などを実施しています。
※「はばたき」(概要パンフ)について → はばたきパンフ
※市内にはこの9月から民間の児童発達支援センターも開設予定です
名 称:とりっくおあとりーと府中
住 所:東京都府中市八幡町2-4-17共栄ビル1階
サービス:児童発達支援
~近年、発達障害をかかえる児童が増えるなか、こうした施設への需要と保護者の方がたらの期待が高まっているだけに、今回の政府方針について、支援員の拡充と充実、具体化が期待されます。~
以前、私も厚生委員会において、児童発達支援員について若干質疑をしたことがありますので、以下、掲載します。
●ゆうきりょうの質疑⇒発達支援センターには児童相談支援専門員やスクールソーシャルワーカーの配置については考えていますか?
●市の答弁⇒直接的な配置は考えてないが、専門医との連携は必要と考えている。発達支援センターと子ども家庭支援センター「みらい」との連携は行う。
●ゆうきりょうからの要望・・ペアレントメンター育成のためのe-learnig受講の費用助成を要望したい。
※府中市の令和7年度予算案について、市民のみなさんから要望を受け付けております。10月25日ぐらいまでにメールでお寄せください。匿名希望でも結構です。 ★要望内容の例・・街のライフライン(鉄道駅、バス停車場、道路、信号、カーブミラー設置、公共施設など多数)、市の福祉制度に関すること、小中学校に通うお子さんに関すること、幼稚園、保育所、学童保育、介護、障害者福祉、公共行政のサービスに関することなど、なんでも結構です。※ただし要望内容によっては、私のほうで整理修正、あるいは取捨選択する場合もありますが、どうかご了承ください。 メールアドレス yuki4551@ozzio.jp まで