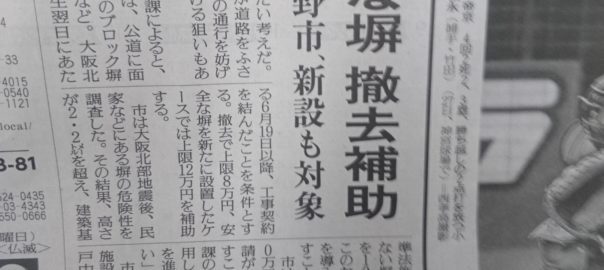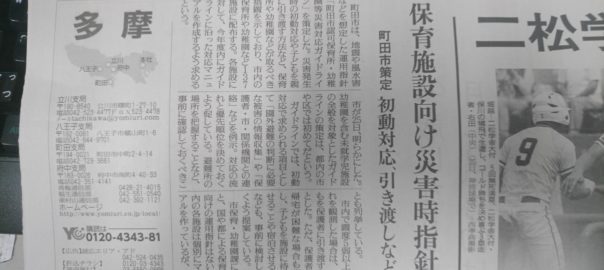民間のブロック塀を多摩市が無料点検

【東京新聞多摩版の報道から】
先日の大阪北部地震でコンクリートブロック塀が倒れ、女児が死亡したのをうけ、多摩市では民間が所有する市内のブロック塀を無料で安全点検するとの記事があります。記事では「都内の区市町村で初めての取り組み。1件あたり15000円を見込む点検費用は、市の予備費で負担」とあります。また「不特定多数の市民が通る公道、私道沿いのブロック、レンガ、石積みの塀や門柱が対象。所有者か管理者が申請すると、市の選任した一級建築士などの専門家が外観から点検する」とし、2020年まで続けるとのこと。またこの点検で、安全性が不十分だった場合は改修費を補助できるように、9月補正予算案で経費を計上することも検討しているとあります。
府中市では学校の塀についての安全対策は機敏に行われていますが、今後はこの民間が所有する塀の安全性についても、その対策が急がれると思います。府中市でもぜひ、この多摩市の実例を参考にして、対策を講じるようしてほしいものと思います。この安全塀対策は今度の9月議会の一般質問や、決算特別委員会でも議論になるのではないでしょうか。私も他市の動向や情報を集めながら、府中市に対して取り上げたいと思います。結城亮(結城りょう)