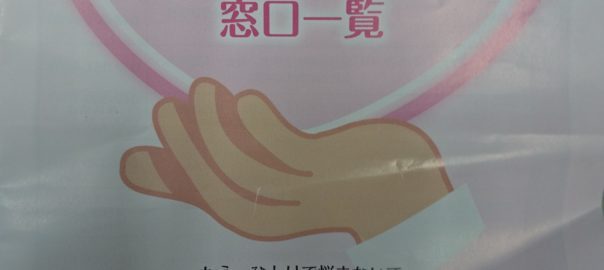府中市が「若年性認知症ガイド」を発刊しました・・ぜひご活用ください
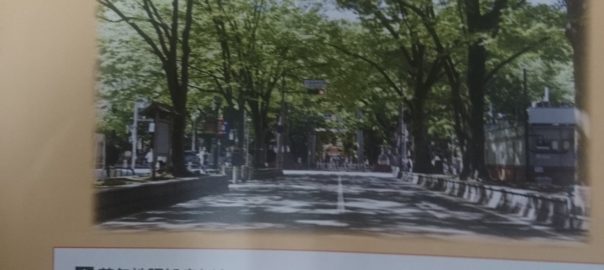
府中市議会議員の 結城りょう です。
府中市は増え続ける若年の認知症について、市独自のガイドブックを発行しました。これまで認知症といえば一般的に、高齢者の方の病気というイメージでしたが、近年は65歳未満の方でもなる病気です。
確かに私の学生時代の友人も以前、「最近自分が認知症かもしれない」と話し、「先日も、お昼ご飯を食べたことを忘れてしまい、再度食べに行こうとしてしまった」と体験を話していました。たとえば「昨日の昼食は何を食べたかな?」というのは、物忘れだと思います。しかし昼食を食べたこと自体を忘れてしまい、再度昼食を食べに行こうというのは、確かに認知症の症状のひとつではないでしょうか。
今回の府中市のガイドでは、①高齢者と若年性認知症との違い、②若年性認知症の疑われる症状、③若年性認知症と診断されたケースの対応について、④本人や家族を支える仕組みと関係機関、⑤利用できる制度やサービスの相談窓口、⑥相談や対応ができる市内の包括地域支援センター、介護支援マップなども詳しく掲載しています。関心のある方は、府中市の高齢者支援課地域包括ケア推進係
電話042-335-4537 へ
★結城りょう 街頭市政報告&相談会
(朝)6時前から8時まで 月曜・・西武線多摩駅、火曜・・府中駅北口デッキ、水曜・・東府中駅北口、木曜・・府中駅北口デッキ、または西武線多摩駅、金曜・・JR北府中駅歩道橋 ※雨天時は中止の場合あり (夕方)毎週2~3回、16時前後から17時前後まで 場所は府中駅周辺、今後はスーパーライフ東府中店付近も予定