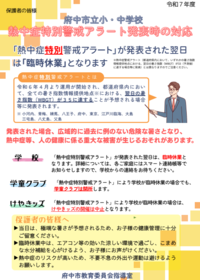府中市 フリースクールへの独自補助を・・都内でフリースクールへの独自支援策をする自治体が増える傾向(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。
不登校児童、生徒が全国的にも増え続けていますが、東京都ではフリースクール助成金をスタートさせて、さらに都内の自治体ではそれに上乗せして、助成金が開始されています。同時に「東京都フリースクール助成金が開始(最大2万円)されてから、近隣のフリースクールが全体的に値上げされています」とのお声を、保護者の方からいただいています。
■助成金額(月額)自治体
助成金額(目安)①品川区 最大2万円、②港区 最大2万円、③品川区 最大2万円、④北区 最大1万円、⑤荒川区 最大2万円、⑥足立区 最大2万円、⑦葛飾区 最大1万円、
※港区 https://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikushien/minatofs.html
※北区 https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/education/1008137/1018626.html?utm_source=chatgpt.com
※荒川区 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a050/kyouiku-seishounen/kyouikushien/hojyokinn.html
※足立区 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kyoikushido/freeschool-josei.html
※葛飾区 https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000057/1002475/1036500.html
※品川区 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kukyoi/kukyoi-futouokutaisaku/hpg000000893-2.html
★東京都が24年度予算から12億円を計上、1500人を対象にフリースクール支援補助を開始
23年9月の朝日新聞に、東京都が小中学生の不登校支援として、フリースクールの利用料について最大2万円の助成をする方針を決めたとあります。記事によると「都は新年度予算案に12億円を計上、対象は約1500人を見込む」「フリースクールの団体や利用者向け支援は茨城県、札幌市などで例はあるが、都の取り組みは対象人数や事業総額の規模が大きい」とのことです。
この記事にもありますが都内の公立小中学校の不登校児童生徒数は過去最多の計2万6912人を記録、フリースクールの授業料は月額平均約4万5千円との調査結果があるとのことです。
府中市内は現在、フリースクールが数校ありますが、不登校児童、生徒が増え続けている今日、さらに増えると思われます。その意味で東京都の施策は意義あるものです。また府中市内の不登校児童生徒数は過去最高の500人を超える数を記録、その居場所づくりが課題になっています。市の現状の施策、放課後児童クラブ、市内文化センターにある児童館などの施設だけでは、そのニーズを満たすことはできません。ぜひ官民協働、市民協働による不登校児童対策を求めたいものです。
★東京都のフリースクールの補助金について・・使い勝手の悪い制度では負担は軽くならない(保護者の声から)
子どもの第三の居場所について、なかでも不登校児童生徒の居場所の確保と対策について、こども家庭庁も新たな方針を示しており、今後、自治体の施策の充実が問われてきます。そこで市民の方から、おもにフリースクールの課題についてお声をいただきましたので、以下紹介させていただきます。
~東京都のフリースクール研究費についてお話させていただきます。自治体によっては独自にフリースクールの補助金があるようです。東京都の事業は、期限や期間があるため、利用できない期間が発生します。家庭の負担が大きくなります。
鎌倉市の例を上げますと、利用した金額に応じて最大1万円のお支払いがあるようです。しかし、フリースクールで利用した金額だけを保証されても、帰りに申し送りを聞くこともあること、1人では通えないので、送迎を朝晩する必要があります。交通費として、電車、バス、ガソリン代、場合によっては駐車場代ががかかることもあると思います。
★学校給食無償化の次はフリースクールなど子どもの居場所確保策の充実
不登校では、外に出ることも抵抗がありますので、電車やバスは、その日の体調で利用できないお子さんもいると思います。目的地まで車なら通えるというお子さんもいます。特性のあるお子さんが定型発達のお子さんのように通えると思うのは違うと思います。フリースクールの利用料金だけを全てとして、鎌倉市のように補助を見てほしくないと思います。 また府中市においては、フリースクール自体が少ないですので、他市を選んでいる方が圧倒的に多い印象です。自治体でもそうですが、給食費の次は、こういったサポートにも期待したいです。(以上、保護者の方の声から)
~フリースクールについては、不登校のお子さんをもつ保護者の方から、その金銭的負担が重くて、通わせることができないというお声をいただきます。子どものコミュニケーションを育む場としての、フリースクールは貴重な場です。自治体で開設されている、不登校支援校などへアクセスできない子どもたちのためにも、ぜひ支援策について、要望していきたいと思います。(府中市議 国民民主党 ゆうきりょう)
※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp 電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202
※ ゆうきりょう の朝の駅頭市政報告は、原則、毎朝下記の予定で行っています。駅頭では「市政通信」を配布しています。市政相談、生活相談なども受け付けています。なお雨天時や、自身の都合により中止の場合もあります。お気軽にお声をおかけください。
月曜日・・西武線多磨駅東口
火曜日・・京王線多磨霊園駅南口
水曜日・・京王線東府中駅北口
木曜日・・西武線多磨駅西口
金曜日・・京王線多磨霊園駅北口
※原則、朝8時まで