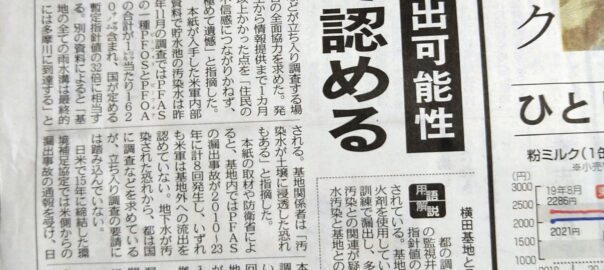府中市 京王電鉄が全駅に安全ホームドアの設置を実施へ・・府中市内の京王線の駅に安全ホームドアが設置へ

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。
京王電鉄のHPによると、同社は「さらなる安全性の向上を目指すべくホームドアの設置を進める」とあり、「この度、さらなる高度な安全、安心を実現させるため、お客様の安全性と列車運行の安定性確保の観点から、京王線全駅へのホームドア整備を決定いたしました。ホームドアの整備に際しては、バリアフリーの観点から、列車とホームとの間の段差および隙間を縮小する対策も同時に実施します」と伝えています。
★鉄道の自動運転化ともあわせて、安全ホームドアの設置を実施へ
また同社HPではさらに続けて「ホームドア整備によりホーム上の安全性が向上することから、自動運転化の推進に向けて自動運転設備の整備工事に着手することを決定いたしました。これにより、将来予測される生産年齢人口減少や働き方改革がさらに進行した事業環境下においても、鉄道輸送の安全およびサービスレベルを確保しながら持続可能な鉄道事業を目指してまいります」との運営方針をお知らせしています。また日経ニュースによると「45駅分の総事業費のうち、ホームドア工事に669億円を、自動運転化に向けた工事に162億円を振り向ける見込み」とsのことです。
私もこの間、市議会の予決算委員会をはじめ、市長あての予算要望書のなかで。府中市内の京王線沿線のホームに安全ホームドアの設置を要望してきましたが、市の回答は「東京都の予算措置という状況をかんがみて、鉄道会社に要望したい」との趣旨の中身でした。ホームからの転落事故があるごとに、「安全ホームドアがあったら防ぐことができたのに」と思われる方は多かったと思いますが、今回、京王電鉄が全駅に安全ホームドアの設置を実施していくことで、この問題が解決すると思われます。
また東京都の小池知事も先の都知事選挙において、都内全駅に安全ホームドアの設置の推進を公約の1つに掲げていたこともあり、事態が動いたと思われます。(府中市議会議員 ゆうきりょう)
※府中市議会議員 ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp